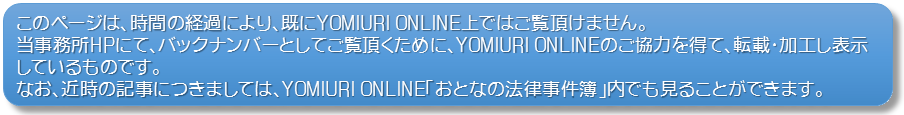転勤辞令、「子どもの通学」理由に拒否できる?
相談者 T.Kさん
私はとある中堅商社の人事部長を務めています。本店は東京で、北海道から鹿児島まで全国20か所に支店、出張所があります。今年就任した社長が地方のテコ入れを打ち出したこともあり、来年の人事異動は大変なことになりそうです。そんな中、先日こんなことがありました。
横浜支店に勤務する中堅社員Aが会議のため本店に来たので、「コーヒーでも」と言って休憩室に誘い、「横浜でのプロジェクトもそろそろ一段落したころだろう。来年2月から所長として鹿児島出張所に行ってくれないか」と打診したのです。Aが黙っているので、「君はなかなかのやり手だと幹部も評価している。小なりといえども一国一城の
家庭を大切にする今の風潮はわかっているつもりです。でもわが社の就業規則には、「業務の都合により異動を命ずることがあり、社員は正当な理由なしに拒否できない」と明記されており、従業員、特に営業担当者の転勤は頻繁に行われています。それにAは、入社時に勤務地を限定するような特別の取り決めをしたわけではありません。
Aはこれまで営業部員として様々な勤務地で勤務してきたのに、急にこのようなことを言われて当惑しています。他の社員は家庭環境に関係なく人事異動を受け入れていることもあり、今回のことが前例になると、会社の人事が滞ってしまうおそれもあります。会社による転勤の辞令について、法律上、社員は争うことができるのか、これまでの例とあわせて教えてください。(最近の実例をもとに創作したフィクションです)
(回答)
転勤=企業戦士の宿命?
サラリーマンであれば、長い会社員生活の中で、「転勤」といった配置転換を命じられることは一般的なことですが、それによって、生活や職場の環境が変わることは言うまでもなく、対象者の生活設計に大きな影響を与えることになります。既婚女性を対象としたある調査によると、配偶者が転勤になった場合に同行しないと回答した人が約3割を占めたとのことであり、その理由としては、相談にも出てくる「子供の学校を替えたくない」との理由のほか、「自分の仕事がある」「現在住んでいる地域から離れたくない」「持ち家がある」などといった回答が多くを占めています。
以前であれば、会社からの転勤の辞令に対して拒否するという選択肢などは全くなく、また家族もたとえ内心は望んでいないとしても一緒に転勤先に同行するというのが、日本企業では当たり前でしたが、そういった状況は徐々に変わってきているということかと思います。
今回は、こうした転勤命令がどこまで許されるかについて、法律面から説明してみたいと思います。
配置転換とは
同一企業内で、労働者の職種や職務内容、または勤務場所のいずれかまたは両方について、長期にわたって変更する人事異動のことを「配置転換」(配転)といいます。そのうち、勤務場所の変更を伴うことを「転勤」と言います。
配置転換は、<1>企業の特定部署に欠員が生じたり、特定部署の業務が増大して現在の人員では対応できなくなったような場合に随時その補充のために実施されたり、<2>定期人事異動の一環として、労働者のキャリアに応じての昇進等を伴って実施されたり、<3>雇用調整措置として、不採算部門に生じた余剰人員を採算の見込まれる部門に異動させることを目的として実施されたりします。
企業は、経営上、組織を効率的に運用するとともに、多種多彩な能力や経験を有した人材を育成する必要があることから、適切な「配置転換」を行う必要があります。ただ、そのような必要が認められるとしても、転居を伴う配転、すなわち転勤命令は、社員(およびその家族)の生活関係に極めて大きな影響を与えることから、従来、様々な紛争を引き起こしてきました。
特段の事情がない限り、権利の濫用にならない
裁判所は、就業規則の根拠規定などを通して、転勤命令権が労働契約法上の根拠を有することを前提とした上で、その効力に関して「権利
この点に関するリーディングケースとしては、最高裁判所・昭和61年7月14日判決が挙げられます。事案としては、全国的規模の会社における、神戸営業所に勤務の大学卒営業担当従業員が、母親、妻および長女と共に堺市内の母親名義の家屋に居住しているという事実関係の下で、同従業員に対する名古屋営業所への転勤命令が権利濫用になるかどうかが争われたものです。一審、二審判決が、いずれも、本件転勤命令の業務上の必要性はそれほど強いものではないのに対し、本件転勤命令は従業員に相当の犠牲を強いることになるとし、転勤命令は権利の濫用に当たり、同命令を拒否したことを理由とする懲戒解雇を無効としました。それに対し、最高裁判所は、原判決を破棄して差し戻し、審理のやり直しを命じています。
この判決は、当該転勤命令が労働者に与える家庭生活上の不利益は、転勤に伴い通常甘受すべき程度のものであるとして、本件転勤命令が権利の濫用に当たるということはできないと判示しています。以下、判決の一部を引用したいと思います。
「上告会社の労働協約及び就業規則には、上告会社は業務上の都合により従業員に転勤を命ずることができる旨の定めがあり、現に上告会社では、全国に十数か所の営業所等を置き、その間において従業員、特に営業担当者の転勤を頻繁に行っており、被上告人は大学卒業資格の営業担当者として上告会社に入社したもので、両者の間で労働契約が成立した際にも勤務地を大阪に限定する旨の合意はなされなかったという前記事情の下においては、上告会社は個別的同意なしに被上告人の勤務場所を決定し、これに転勤を命じて労務の提供を求める権限を有するものというべきである……使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合
勤務地が限定される場合
上記最高裁判所判例が、判決文の中で、「労働契約が成立した際にも勤務地を大阪に限定する旨の合意はなされなかったという前記事情の下において」とあえて指摘しているように、労働契約上、勤務地が限定されている場合、労働者が同意しない限り、転勤を命じることは原則としてできません。
また、書面などによる明確な限定がないとしても、採用面接の際に採用担当者に対して、家庭の事情で転勤できない旨を明確に述べて採用担当者も勤務地を限定することを否定しなかったこと、採用担当者が本社に採用の
なお、総合職・一般職のコース別採用や地域限定社員制度では、明示の勤務地限定の特約が認められると考えられています。現在、アベノミクスの一環として、政府が増加させようとしている「限定正社員」(職種や勤務地・勤務時間などを限定した正社員)のうち、勤務地を限定された限定正社員も同様と考えられます。他方、本社採用の幹部候補社員の場合には、勤務場所が特定されていないとして、全国どこにでも勤務する旨の合意が成立していると解されています。
ただ、上記のような幹部候補に限らず、現地の工場で働く人にも他の地方への転勤義務が認められる場合もあります。例えば、食品容器製造販売会社の従業員で茨城県の関東工場に勤務していた人が、会社から広島県福山市の本社工場への不当な転勤命令により退職を強要されたと主張して、得べかりし賃金、慰謝料および会社都合退職金との差額の損害賠償を請求した事件の控訴審判決(東京高等裁判所・平成12年5月24日)は、「被控訴人ら(注:従業員)の本社工場への転勤は、控訴人(注:会社)の経営合理化方策の一環として行われることになった関東工場の生産部門の分社化に伴って生じる余剰人員の雇用を維持しつつ、新製品であるPS製品の開発・製造のために本社工場に新設されたPS-四課及び同五課等の新規生産部門への要員を確保するべく、控訴人の組織全体で行われた人事異動の一環として計画されたものであって、控訴人の置かれた前記のような経営環境に照らして合理的なものであったと認められる。そして、被控訴人らを転勤要員として選定した過程に格別不当な点があったとは認められない。関東工場の近くに生活の本拠を持ち、関東工場の従業員として採用された被控訴人らが遠方の広島県福山市へ転勤することについては、それを容易に受け入れられない各人それぞれの事情があることは、それなりに理解できなくはないけれども、本件全証拠をもってしても、被控訴人らが勤務先を関東工場に限定して採用されたとの事実を認めるに足りないし……規則上も、『会社は業務上の必要があるときは転勤、長期出張を命ずることがある、この場合、社員は正当な理由なくこれを拒むことができない』旨明記されているのであって、被控訴人らもこれを承知した上で勤務してきたものと認められる。そして、被控訴人らが転勤に応じられない理由として述べた前記のような個別事情(注:被控訴人らからは、妻の母親を週1回病院に連れて行っていること、50歳に達し福山での生活や仕事が不安であること、妻の兄夫婦に跡継ぎがなく転勤中の兄夫婦の家に住んでいるため空き家にするわけにはいかないこと、妻が病気で子供も幼いことなどの主張がなされています)も、それ自体転勤を拒否できる正当な理由に当たるとまでいうことができるものではない」とし、転勤義務があると認めています。
権利濫用法理(労働契約法第3条5項)
職種や勤務地の限定に関する合意が認められない場合は、前述の最高裁判所判決のとおり、企業は、原則として従業員の個別の同意なしに、業務上の必要に応じ、その裁量により従業員の勤務場所を決定し、転勤を命じて労務の提供を求めることができることになります。
しかし、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することは許されないとして、実際の転勤命令の有効性については、権利濫用に該当するか否かで判断することとされています。2008年3月に施行された労働契約法第3条5項でも、「労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない」と規定されており、権利濫用となる転勤命令権の行使は無効となるわけです。
では、転勤命令が権利濫用とならないためにはどのような要件が必要となるでしょうか。この点、前述の最高裁判所判決が指摘しているように、「当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であっても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき、若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない」ということが必要となります。
業務上の必要性があること
まず、転勤命令には「業務上の必要性」がなければなりません。ただし、前述の最高裁判所判決は、「業務上の必要性についても、当該転勤先への異動が余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。本件についてこれをみるに、名古屋営業所のA主任の後任者として適当な者を名古屋営業所へ転勤させる必要があったのであるから、主任待遇で営業に従事していた被上告人を選び名古屋営業所勤務を命じた本件転勤命令には業務上の必要性が優に存したものということができる」としており、裁判所は、業務上の必要性について、比較的容易に認めています。
不当な動機・目的がないこと
次に、転勤命令が「他の不当な動機・目的をもってなされたもの」ではないことが必要です。この点は、裁判所でもよく争点となるところです。
前橋地方裁判所・平成23年11月25日判決は、大学や専門学校を運営する学校法人にバス運転手として就労していた人が、学校法人の経営悪化からバス運転業務が事業委託されることになった事業委託先への転籍を拒否したところ、自宅から50キロ以上、元の職場から60キロ以上離れた学校法人が運営する温泉宿泊施設への転勤を命じられたという事案において、「本件配転命令は、結局、A(注:事業委託先)への転籍を拒否した原告(注:バス運転手)に対し、上述したような不利益を負わせて、任意に退職させるなどの不当な動機・目的をもってなされたものであると認めるのが相当である。したがって、本件配転命令は、権利の濫用に当たり、無効であるというべきである」と判示しています。
通常甘受すべき程度を超える不利益が生じないこと
さらに、従業員に対して、「通常甘受すべき程度を超える不利益」を負わせる転勤命令は権利の濫用となります。ただ、裁判所は、家庭生活上の不利益は、転勤に伴い通常甘受すべき程度のものとして、配置転換命令は権利濫用にあたらないとする傾向にあると思われます。
例えば、従業員数約2000人の会社の東京都目黒区所在の技術開発本部に勤務する女性従業員に対し、同八王子市所在の事業所への転勤命令がされた場合において、同従業員が他の会社に勤務する夫および保育園に通う長男と共に同品川区所在の借家に居住しており同所から右事業所へ通勤するには最短経路で片道約1時間45分を要するといった事実関係の下においては、転勤によって同従業員の負うことになる不利益は必ずしも小さくはないが、なお通常甘受すべき程度を著しく超えるとまではいえず、当該転勤命令が権利の濫用に当たるとはいえないとした判例があります(最高裁判所・平成12年1月28日判決)。この事案では、配転先が同じ東京都内であり、必ずしも転居を必要とするわけではなく通勤も可能です(他社に勤務する夫も八王子近辺から通勤することは可能)。他方、幼児を育てる共働きの夫婦にとっては、保育園への送迎の関係で負担が特に大きくなることから、配転拒否の正当性が果たして認められるのかが争われたわけですが、最高裁判所は、配置転換命令は権利濫用には当たらず有効と認めたわけです。
家族の療養・看護の必要性がある場合
なお、「通常甘受すべき程度を超える不利益」を判断するにあたって、家族の療養・看護等の必要性があることが問題となる事案もありますが、この場合には、転勤命令を権利濫用として無効とした裁判例が比較的多く見られます。
札幌地方裁判所・平成9年7月23日決定は、帯広工場勤務の社員が札幌本社工場への転勤命令を受けた事案において、「債権者(注:転勤命令を受けた社員)は、妻、長女、長男、二女と同居しているところ、長女については、躁うつ病(疑い)により同一病院で経過観察することが望ましい状態にあり、二女については脳炎の後遺症によって精神運動発達遅延の状況にあり、定期的にフォローすることが必要な状態であるうえ、隣接地に居住する両親の体調がいずれも不良であって稼業の農業を十分に営むことができないため、債権者が実質上面倒をみている状態にあることからすると、債権者が一家で札幌市に転居することは困難であり、また、債権者が単身赴任することは、債権者の妻が、長女や二女のみならず債権者の両親の面倒までを一人で見なければならなくなることを意味し、債権者の妻に過重な負担を課すことになり、単身赴任のため、種々の方策がとられているとはいえ、これまた困難であると認められる。そして、債権者が右のような家庭状況から、札幌への異動が困難であることに加えて、帯広工場には、協調性という付随的要件に欠けるが、その他の要件を満たす者が他に5名もいることを考慮すると、これらの者の中から転勤候補者を選考し、債権者の転勤を避けることも十分可能であったと認められるから、債務者(注:会社)は、異動対象者の人選を誤ったといわざるをえず、債権者を札幌へ異動させることは、債権者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるというベきである」としています。
また、東京地方裁判所・平成14年12月27日決定は、Y社の東京本社に勤務するXが、大阪支社への転勤命令を、共働きの妻がいること、2人の子が重度のアトピー性皮膚炎で東京都内にある治療院に週2回通院していること、および将来的に両親の介護の必要があること等を理由に拒否したという事案において、「改正育休法26条は、『事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない』と定め、労働者の子の養育や家族の介護の状況に対する配慮を事業主の義務としているところ、事業者の義務は『配慮しなければならない』義務であって、配転を行ってはならない義務を定めてはいないと解するのが相当である。しかしながら、改正育休法の制定経緯に照らすと、同条の『配慮』については、『配置の変更をしないといった配置そのものについての結果や労働者の育児や介護の負担を軽減するための積極的な措置を講ずることを事業主に求めるものではない』けれども、育児の負担がどの程度のものであるのか、これを回避するための方策はどのようなものがあるのかを、少なくとも当該労働者が配置転換を拒む態度を示しているときは、
ちなみに、上記判例に出て来る「育休法」とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」のことであり、2009年に改正され、家庭的責任を有する労働者への保護・配慮規定が整備されています。2008年3月に施行された労働契約法第3条3項でも、「労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする」として、ワークライフバランスに配慮された規定が置かれており、今後、これらの法律に配慮することなく行われた配置転換命令は、権利濫用とされる可能性が高くなると考えられます。
「子供が私立学校に通っており転校は難しい」だけでは無理
相談者の会社でも、特定社員に対して、横浜支店から鹿児島出張所への転勤を内示したところ、その社員が「子供が私立学校に通っており、転校は難しいので、仮に私が転勤となると単身赴任となってしまう」という家庭の事情を理由に転勤を拒否してきたとのことです。また、その社員は入社時に勤務地を限定するような特別の取り決めをしているわけでもなく、入社してからこれまで、様々な勤務地で営業部員として勤務してきたということです。
冒頭でご紹介した最高裁判所・昭和61年7月14日判決では、全国的規模の会社の神戸営業所勤務の大学卒営業担当従業員が、母親、妻および長女と共に堺市内の母親名義の家屋に居住しているといった事実関係の下で、転勤命令が権利の濫用に当たるということはできないと判示していることからしても、転勤拒否の理由が本当に「子供が私立学校に通っており、転校は難しいので、仮に私が転勤となると単身赴任となってしまう」という事情だけなのであれば、従来の裁判の傾向からみて、転勤に伴い通常甘受すべき程度のものとされて、当該転勤命令が権利濫用に当たることはないだろうと考えられます。つまり、相談にある転勤命令は、会社の裁量権の範囲内と考えられるわけです。そういう意味では、問題となっている社員が、会社からの転勤命令が権利濫用だと主張して争うのは難しいと思われます。
ただ、相談者としては、本当にそれだけが転勤拒否の理由なのかについて十分に確認することは必要です。前述の札幌地方裁判所・平成9年7月23日決定(長女が躁うつ病(疑い)、二女が脳炎の後遺症で精神運動発達遅延の状況などである事案)において、当該社員は、その事情を会社にあらかじめ説明しておらず、その点、裁判所は、その判断において「債権者は、右のような家庭状況を、転勤の内示を受けるまで債務者に申告せず、却って、長女、二女及び両親に何らの問題もないかのごとき家族状況届を提出し、債務者をして転勤の人選を誤らせており、その対応には遺憾な点が存するが、結局、本件転勤命令が出される1か月以上前には債務者に対し家庭状況を申告し、転勤には応じ難い旨伝えていることを考慮すると、債権者の右対応によって右認定が左右されるものではない」と判示しています。社員の側からすれば、このような深刻な家庭内の事情はなかなか勤めている会社には報告しにくいものであり、後からそのような事情が出て来ることもあり得ますから、単なる社員のわがままと切り捨てるのではなく、十分な事情聴取をして、誠意ある対応を行うことは必要ではないかと思われます。