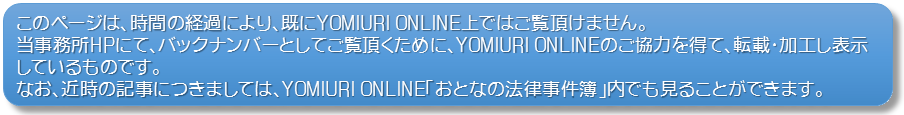会社の就業時間外に副業、問題は生じる?
相談者 F.Mさん
私は、小売り関係の一般企業に勤務しています。若いころから、忙しい時期は残業も当たり前だと思ってがむしゃらに働いてきました。給与明細を見た妻がびっくりするほど残業代も稼ぎましたし、「あいつは使えるヤツだ」と上司の受けもよかったと思います。ところが最近、風向きが変わってきました。うちの会社も、社長の号令のもと、ワークライフバランスの推進に非常に熱心に取り組み始めたのです。
仕事は定時で終え、休日出勤はしないよう通達がありました。おまけに時間外勤務が多いと上司から注意され、評価にも影響します。私も午後6時になると、いそいそと帰り支度をするようになりました。普通ならば、家族で団らんの一時を過ごすとか、趣味の時間にあてるとかになるのでしょうが、企業戦士として働き続けて来た身としては、物足りなさを感じるばかりです。
そこで、最近よく話題に出てくる「サラリーマン大家さん」になるべく、会社を設立して、不動産を購入し大家さん業を始めようと思いたちました。サラリーマンで安定した収入があると、融資も受けやすいようです。定年退職後は、年金に頼らざるを得ませんが、年金制度が崩壊しても何とか暮らしていけるだけの一定の副収入があれば、老後も安心ですから妻も賛成してくれています。
そこで気になるのが、会社の就業規則に掲載されている、兼業を禁止する旨の規定です。私としては、就職以来お世話になっている会社の仕事をおろそかにする気など全くなく、会社が終えた後や、週末の土曜・日曜など、会社の仕事に影響が出ない範囲で働くことを考えているので、特に問題ないだろうと考えているものの、何となく不安です。一時期、「週末起業」という言葉がブームになり、そういったセミナーも開催されるなど、社会では、サラリーマンの副業に対する認知度も高まっていると思いますが、副業を始めることで、会社との関係で何か問題が生じる可能性があるのか、教えてくれますか(最近の事例をもとに創作したフィクションです)。
(回答)
「サラリーマン大家さん」ブーム
最近、「サラリーマン大家さん」という言葉をよく聞きます。一時期ブームになった「金持ち父さん 貧乏父さん」という著作がきっかけとも言われていますが、普通のサラリーマンが、退職後などに備え、勤めている会社を辞めずに、投資用マンションやアパートなどを購入し副収入を得る「大家さん」業を行うということを一般には指すようです。その背景には、老後の年金などに対する不安があるとのことで、ネット上では、成功例、失敗例、成功するためのノウハウ等の様々な情報があふれています。
なお、相談に出てくる「週末起業」という言葉も一時期よく聞きましたが、サラリーマン大家さんと同様に勤務する会社を辞めることはしませんが、「大家さん」業というより、むしろ主にインターネットなどの新しいツールを利用し、比較的少ない資本で、在宅中心での起業をすることと定義するのが一般的のようです。
いずれにしても、「サラリーマン大家さん」も「週末起業」も、今ある「本業」に対し、いわゆる「副業」を始める、つまり、複数の職業を兼ねること(=兼業)を意味します。今回は、自ら会社を設立して経営する場合ばかりでなく、他の会社に雇われる形態も含め、広い意味で、本業とは別の副業を持ちその両方を行う「兼業」というものが、法律上どのように問題となるのかについて解説してみたいと思います。
兼業容認の方向性
厚生労働省は「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」報告書(2005年9月15日)において、就業規則における兼業禁止規定につき、「使用者は、労働者の兼業を禁止し、
すなわち、現在でも事実上、社員の兼業を黙認している企業は多いでしょうが、相談者のように考える方も含めて、兼業を希望する人が増えている中で、社会全体としては、今後、企業が社員の兼業を許容する方向に進んでいくと思われます。
企業における兼業に対する姿勢
本来、労働者には、憲法第22条が保障する職業選択の自由(営業の自由・勤労の自由)がありますので、兼業であろうと基本的に自由にできるはずです。ただ、公務員については、職務の公正、中立性及び信頼性といった要請から、兼業は法律によって規制されており(国家公務員法第101条、第103条、地方公務員法第38条など)、基本的には認められていません。これに対して、民間企業の労働者については、兼業を特に規制する法律は存在しませんから、職業選択の自由についての議論がそのままあてはまりますし、労働契約上も、労働者は「労働時間中に限って」労務の提供を行うことが主たる義務であるため、労働時間外の私生活をどのように利用するかは、労働者にとり、原則的に自由ということになるはずです。
しかしながら、兼業によって、本来の職務がおろそかになることは本末転倒であり、会社の側としても、社員には、会社の職務に専念してもらいたいという思いがあることから、前述の研究結果にも表れているように、多くの会社の就業規則や労働契約においては、兼業を禁止あるいは許可制(「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」、「会社の承認を得ないで在籍のまま他に就職しないこと」などといった条項)として、たとえ、所定の労働時間外の兼業についてであっても、一定の制限をしているのが実情です。
そのために、兼業の問題は、労働者が兼業をした際に、上記兼業禁止規定に抵触したとの理由により、企業から何らかの懲戒処分が行われた場合に、当該処分が果たして有効なのかという形で法的には問題となってきます。
兼業禁止規定自体の有効性
一般に、懲戒事由に該当すると認められるためには、<1>就業規則や労働契約上の兼業禁止規定自体が有効であること、<2>兼業禁止規定自体が有効であったとしても、同規定が具体的事案に適用されることが適当であること、の2つの検討が必要になります。
<1>の就業規則や労働契約上の兼業(副業)禁止規定自体が有効であるか、の問題は、前記のとおり、営業の自由(職業選択の自由)は憲法で保障された重要な権利であるにもかかわらず、これを制約することが公序良俗に反して、そもそも無効ではないかという問題意識から出てくるものです。
会社に在籍しながら他の会社の採用試験を受けたケース
この問題点に関する裁判例として、まず鳥取地方裁判所・昭和43年7月27日決定を挙げたいと思います。この決定は、会社に在籍のまま他の会社の採用試験を受けた行為について、就業規則で定められた懲戒事由(会社の承認を受けず在籍のまま他に雇い入れられようとしたとき)に該当するとして、懲戒解雇処分を受けた事案です。同事案において、鳥取地方裁判所は、次のように、就業規則における懲戒事由の一部を無効と判断しています。
「本件においては申請人(注:労働者)が被申請人(注:会社)の承認を得ずして他に雇い入れられるべく他社の面接試験を受けたことが懲戒解雇事由たる前記就業規則第44条第8号(注:会社の承認を受けず在籍のまま他に雇い入れられ又は雇い入れられようとしたとき)後段の規定に該当するとして申請人を懲戒解雇したものであることはさきに認定したとおりであるが、右懲戒権の行使はそれが労働者に何らかの不利益を科すものである以上、その程度、方法が企業の経営秩序を維持し、業務の円滑な運営を確保するために、客観的にみて必要、最小限にとどめられるべきものであると解するのが相当である……被申請人にとっても同条前段の『他に雇い入れられたとき』とは異なり、
多くの裁判例では、兼業禁止規定自体は有効と判断
上記鳥取地方裁判所の事件では、兼業禁止規定の一部そのものが無効であるとの判断になりましたが、実は、多くの裁判例は、事情のいかんを問わずに絶対的に兼業を禁止するような内容でない限り、規定自体の合理性は認め、就業規則の兼業禁止規定自体は有効であると判断しています。
東京地方裁判所・昭和57年11月19日決定は、事務員として会社に勤務していた者が、会社の勤務時間である午前8時45分から午後5時15分までの勤務(本社・外回りの社員・顧客からの電話連絡の処理、営業所内の清掃、本社と営業所との通信事務、営業所内の書類整理など)を終えた後、午後6時から午前0時まで、キャバレーでホステスや客の出入りをチェックするリスト係または会計係として勤務したことが問題となった事案です。会社は、この就労の事実を知り、会社就業規則(会社の承認を得ないで在籍のまま他に雇われたとき)に該当しているとして解雇し、裁判に発展したわけですが、裁判所は、次のように判示して、会社の主張を認めています。
「法律で兼業が禁止されている公務員と異なり、私企業の労働者は一般的には兼業は禁止されておらず、その制限禁止は就業規則等の具体的定めによることになるが、労働者は労働契約を通じて一日のうち一定の限られた時間のみ、労務に服するのを原則とし、就業時間外は本来労働者の自由であることからして、就業規則で兼業を全面的に禁止することは、特別な場合を除き、合理性を欠く。しかしながら、労働者がその自由なる時間を精神的肉体的疲労回復のため適度な休養に用いることは次の労働日における誠実な労働提供のための基礎的条件をなすものであるから、使用者としても労働者の自由な時間の利用について関心を持たざるをえず、また、兼業の内容によっては企業の経営秩序を害し、または企業の対外的信用、体面が傷つけられる場合もありうるので、従業員の兼業の許否について、労務提供上の支障や企業秩序への影響等を考慮したうえでの会社の承諾にかからしめる旨の規定を就業規則に定めることは不当とはいいがたく、したがって、同趣旨の債務者(注:会社)就業規則第31条4項の規定は合理性を有するものである……債務者就業規則第31条4項の規定は、前述のとおり従業員が二重就職をするについて当該兼業の職務内容が会社に対する本来の労務提供に支障を与えるものではないか等の判断を会社に委ねる趣旨をも含むものであるから、本件債権者(注:労働者)の兼業の職務内容のいかんにかかわらず、債権者が債務者に対して兼業の具体的職務内容を告知してその承諾を求めることなく、無断で二重就職したことは、それ自体が企業秩序を阻害する行為であり、債務者に対する雇用契約上の信用関係を破壊する行為と評価されうるものである。そして、本件債権者の兼業の職務内容は、債務者の就業時間とは重複してはいないものの、軽労働とはいえ毎日の勤務時間は6時間にわたりかつ深夜に及ぶものであつて、単なる余暇利用のアルバイトの域を越えるものであり、したがって当該兼業が債務者への労務の誠実な提供に何らかの支障をきたす蓋然性が高いものとみるのが社会一般の通念であり、事前に債務者への申告があった場合には当然に債務者の承諾が得られるとは限らないものであったことからして、本件債権者の無断二重就職行為は不問に付して然るべきものとは認められない……これらの事情を総合すれば、債務者が前記債権者の無断二重就職の就業規則違背行為をとらえて懲戒解雇とすべきところを通常解雇にした処置は企業秩序維持のためにやむをえないものであって妥当性を欠くものとはいいがたく、本件解雇当時債権者は既に前記キャバレーへの勤務を事実上やめていたとの事情を考慮しても、右解雇が権利濫用により無効であるとは認めることができない」
どの様な行為が兼業禁止規定に違反するのか
上記東京地方裁判所決定が指摘するように、「労働者は労働契約を通じて一日のうち一定の限られた時間のみ、労務に服するのを原則とし、就業時間外は本来労働者の自由である」わけですから、従業員が何か兼業をすれば、当然に同規定に該当するという判断になりません。つまり、兼業禁止規定自体が有効であるとしても、同規定が適用されることが適当であるか否かにつき、当該行為の性質、態様を考慮したうえで、兼業禁止規定を限定的に解釈して、適用の当否を考えなければならないということです。
裁判所は、「会社の企業秩序に影響せず、会社に対する労務提供に格別の支障を生ぜしめない程度のものは含まれない」(浦和地方裁判所・昭和40年12月16日判決)とするなどして、基本的に、兼業禁止規定を限定的に解釈しています。つまり、裁判では、会社の職場秩序に影響せず、かつ会社に対する労務の提供に格別の支障を生ぜしめない程度・態様の兼業は、兼業禁止規定の違反とはいえないとする一方、そのような影響・支障が認められるものは禁止規定に違反し、懲戒処分の対象となると解しているわけです
具体的に見てみると、前述した東京地方裁判所決定でも、形式的な兼業禁止違反行為があっただけで規定違反に該当すると判断してはおらず、兼業の職務内容が、軽労働とはいえ毎日の勤務時間は6時間という長時間に及び、かつ深夜に及ぶものであるとの実態を見て、当該兼業が本業における労務の誠実な提供に何らかの支障をきたす可能性が高いことから、兼業禁止規定に該当することを認め、懲戒処分を有効としているわけです。
また、病気による休業中にオートバイ販売店を開業して経営していた事案において、東京地方裁判所八王子支部(平成17年3月16日判決)は、「原告が本件オートバイ店開店に至る動機、申請等の名義、開店にあたっての原告のリスク、営業状況等の諸事情を併せ考慮すると、本件オートバイ店は、原告が、家族の生活を維持するために、自ら開店、経営し、原告の労働力なしではその営業が成り立たないものであり、原告には、長期にわたる経営意思があって、もはや、今後、被告において就労する意思はなかったものと認めるのが相当である。そうすると、原告が、被告から給与を一部支給されたまま本件オートバイ店開店・営業していた行為は、会社の職場秩序に影響し、かつ被告従業員の地位と両立することの出来ない程度・態様のものであると認めるのが相当である」としたうえで、「原告の本件オートバイ店経営・就労は、就業規則53条3項8号の懲戒解雇事由である『会社の承認を得ないで在籍のまま、他の定職に就いたとき』にあたり、原告には就業規則上の懲戒解雇事由が認められる」とし、懲戒解雇を認めています。
さらに、労働者が、使用者と競業関係に立つ他の会社の取締役に就任した場合には、たとえその労働者が会社の経営に直接関与していなかったとしても、使用者の企業秩序をみだし、またみだすおそれが大であるから右の労働者に就業規則の規定(「会社の承認を得ないで在籍のまま他に雇入れられ他に就職した者」を解雇する旨の規定)を適用して解雇することができるものとした判例(名古屋地方裁判所・昭和47年4月28日判決)などもあります。
兼業禁止規定違反とならなかった事案
他方、兼業禁止規定違反と認定されなかった次のような事案もあり、結局は、事案ごとの判断となるわけです。
<1>病気休職中の女子工員が知人の依頼により、かつ復職にそなえて体をならすために10日間、1日2、3時間工場を手伝ったという事案について、労務の提供に格別の支障を生ぜしめないかぎり懲戒処分は認められないとした事案(浦和地方裁判所・昭和40年12月16日判決)。
<2>タクシー運転手が、就業前、毎朝、父親の経営していた新聞販売店で2時間新聞配達をしていたことを理由として
<3>貨物運送会社の運転手が、年に1、2回の貨物運送のアルバイトをしたことを理由とする解雇に関し、アルバイト行為が業務に支障を来しておらず、職務専念義務違反とまでは言えず無効とした事案(東京地方裁判所・平成13年6月5日判決)。
<4>就業時間が午前8時から翌日の午前2時までで、勤務終了の日が非番日となっているタクシー会社の乗務員が、会社に無断で、非番日の午前8時から午後4時45分まで輸出車の移送、船積み等をするアルバイトを1か月平均7、8回行っていたという事実関係について、「債務者(注:タクシー会社)が債権者(注:乗務員)に対し何らの指導注意をしないまま直ちになした解雇は(懲戒解雇を普通解雇にしたとしても)余りに過酷であり、解雇権の濫用として許されない」とした事案(広島地方裁判所・昭和59年12月18日決定)。
裁判例からみる基準の整理
以上を整理すると、就業規則における兼業禁止規定が全くの無限定であるとか、適用範囲が広範囲に及ぶような場合には、兼業禁止規定自体を無効とすることもあり得ますが、むしろ、多くの場合には、兼業禁止規定自体は有効としつつ、当該事案において、兼業内容の期間や時間の長短、会社の勤務に支障が生じるか否か、兼業の態様や営利性などの観点を踏まえて、当該兼業禁止規定が適用される場面を「会社の企業秩序に影響せず、会社に対する労務提供に格別の支障を生ぜしめない程度のものは含まれない」と限定的に解釈して、個別具体的な判断がなされるものと思われます。また、例えば競合他社での兼業や、会社の営業技術やノウハウが漏えいされるような兼業、兼業として違法な仕事をするなど、会社の信用や品位を害するものなどについては、兼業禁止規定が適用されると考えられます。
兼業をはじめるならきちんと社内手続きを取ってから
本相談では、相談者の会社の就業規則における兼業禁止規定の内容は明確ではありませんが、前記のとおり、当該規定自体が無限定で無効とされることは通常ありませんので、兼業禁止規定自体は有効であるという前提で考えた方が良いと思います。
そして、その場合、例えば、会社が他の社員も含めて一定の兼業を黙認してきたというような社内慣行がある場合(兼業禁止規定が有名無実化しているような場合)はもちろん、前述の判例の傾向としての「会社の企業秩序に影響せず、会社に対する労務提供に格別の支障を生ぜしめない」兼業である限りは、兼業禁止規定に違反しているとまで言うことはできず、これを理由として会社が懲戒処分にすることは難しいと言うことができます。
そういう意味では、相談者は、「就職以来お世話になっている会社の仕事をおろそかにする気など全くなく、会社が終えた後や、週末の土曜・日曜など、会社の仕事に影響が出ない範囲で働くことを考えている」とのことであり、また、本業である小売り関係の会社の業務と競業するものでもなく、会社の営業技術やノウハウが漏えいされる恐れもありませんから、相談者が、兼業禁止規定に違反しているとして懲戒処分を課される可能性は低いと考えられます。
ただ、会社の就業規則に、兼業禁止が明示されているにもかかわらず、社内手続きを取らずに無許可で兼業を行なうことが、形式上、就業規則違反となることは明らかです。前述のように、兼業禁止規定自体の有効性が多くの裁判で認められている以上は、勝手に自分で「会社の企業秩序に影響せず、会社に対する労務提供に格別の支障を生ぜしめない」兼業だから問題ない、会社に報告する必要はないと判断してしまうのは問題があると言わざるを得ません。
やはり、兼業を行なう場合は、就業規則に従った社内手続きをきちんと取り、上記のように、会社が実質的に禁止しているような類いの兼業ではないという事を十分説明してから、業務を開始した方がよろしいと思います。相談の事案であれば、仮に、就業規則違反を理由に会社から懲戒処分を受けても、おそらく裁判で争えば勝てるでしょうが、そのような無用なトラブルや負担を、あえて背負う必要は全くないと思います。