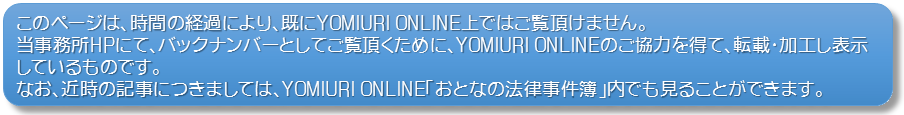ライバル企業の社員の引き抜き、どこまで許される?
相談者 H.Sさん
私は、広告代理店で法務部長として、法律に関すること全般を扱っています。
業務は、例えば、当社が結ぶ契約の中身を点検したり、新規事業を始める際に法律上の問題がないかを調べたり、といったことですが、それ以外に社員の行動にも目を光らせています。そんな私の最近の心配のタネといえば、営業課に不穏な空気が流れていることです。
社内の人脈を使って探りを入れたところ、近く退職する営業課長のTに同調してわが社を去る社員が続出するかもしれないとのことでした。Tは創業以来の生え抜きで、社内外に広い人脈を持ち、わが社の発展に力を尽くしてきました。ライバル社から恐れられる存在だったのですが、多少自信過剰になったのでしょう。社の許可なく経済系の週刊誌の取材を受け、デカデカと載った記事が社長の
部下の面倒見がよかったTは、社内の人望も厚く、行動をともにしたいという社員がいても不思議ではありません。気になるTの転職先ですが、破格の条件でライバル社に移籍するというのがもっぱらの
(回答)
藤田社長の激怒が話題に
アメーバブログ関連の事業やインターネット広告代理店事業を展開する「サイバーエージェント」(本社・東京都渋谷区)の藤田晋社長が、競合企業から引き抜かれた、ある社員に対して「激怒」し、しかも社長が怒っているという噂が社内に拡散するよう意図的に怒ったことを報告した内容のブログが話題になっています。藤田社長は、「辞めた社員のことを憎く思って激怒したわけではありません。正直言えば『かわいそうなことをした』と思っています。それでも大勢の社員を率いる立場として、組織の未来のために、あえて
藤田社長によれば、2000年頃、他社社員の引き抜き行為を行った際に、業界2位以下の会社は寛容だったのに対して、業界1位の会社は「出入り禁止」とばかりにカンカンに怒り、その企業は今でも業界首位を堅持しているという事例を挙げ、「長い目で見れば、社会に対しても社員に対しても、良い会社とは永続性のある強い会社のことだと思っています。そのためには、優秀な人材を競合(他社)には渡さない、という毅然とした態度も必要だということに、その時、気づきました。それから私は、不寛容と言われようが、社員が同業に引き抜かれた場合は『激怒する』という方針を決めたのです」とも書いています。
このブログに対しては、社長が社員個人を、対象者を特定できるような形で批判したことについて疑問を呈する意見や、経営者としての率直な考えに賛意を示す意見などが入り乱れており、しばらくは世間の話題になりそうです。
藤田社長は著名なインターネット企業のトップだけあって、常時、様々な情報をネットはもちろん、書籍などを通じて発信しており、自分の発言がこのような事態になることは当然想定していたと思われますが、この事態を受けて、次にどんな発言をするのか興味深いところです。
そこで、今回は、藤田社長のブログを契機に盛り上がっている、社員の引き抜き行為に関する法律問題について解説してみたいと思います。
社員の転職は原則自由
まず、そもそも社員の転職は自由に認められるのでしょうか。この点、憲法第22条1項は、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と規定しています。つまり、従業員が転職すること自体は、「職業選択の自由」により認められており、会社が阻止することは原則として許されません。
この点に関してよく問題となるのが、就職時や退職時において、「会社を退社してから〇年間は、競業する企業への就職をしません」といった条項が入っている誓約書を提出している社員が、当該会社を退職する場合、その誓約書での取り決め事項が有効なものとして機能するのかという点です。
奈良地方裁判所・昭和45年10月23日判決は、「一般に雇用関係において、その就職に際して、或いは在職中において、本件特約(筆者注:「Aは雇傭契約終了後満2年間B社と競業関係にある一切の企業に直接にも間接にも関係しないこと」との特約)のような退職後における競業避止義務をも含むような特約が結ばれることはしばしば行われることであるが、被用者に対し、退職後特定の職業につくことを禁ずるいわゆる競業禁止の特約は経済的弱者である被用者から生計の道を奪い、その生存をおびやかす
かように、たとえ競業企業への転職を明確に禁じた旨の誓約書などを会社に提出しているとしても、それによって競業企業に転職できないということには必ずしもなりません。社員における職業選択の自由の保証は、それほど重要であるということです。
わずか6か月間の制限であっても無効とされた判例も
例えば、大阪地方裁判所・平成12年6月19日判決では、X社が、同社を退職後、X社と競業関係にあるY社へ就職した元従業員らに対し、X社との雇用契約上退職後6か月間は同業他社などへの就職を禁止されていたにも
このような事案では、どの程度の期間なら有効なのか、どのような代償措置を取れば有効なのかなど、様々な難しい問題があり、裁判の場で争われることも多いのですが、今回のテーマではありませんので、この程度にとどめたいと思います。いずれにしても、企業が、社員の転職を制限することは簡単ではないということです。
では、基本的に社員の転職が自由であるという上記の理屈から、社員に転職を促して引き抜く行為を行うことも同様に自由であると言って良いのでしょうか。
企業による社員引き抜きは原則自由
終身雇用制度という慣行が崩壊し、転職する者も珍しくなくなった最近では、競合企業や、いわゆるヘッドハンターが、優秀な人材を他企業から引き抜くという行為も多く見られるようになりました。そして、社員の転職自体が基本的に認められているのと同様に、企業が、他の企業の社員を引き抜くという行為は、道義的な問題を別にすると、社員個人に退職の自由、職業選択の自由が保障されており、また、競合企業にも営業の自由があり、自由競争の原則の下において、引き抜き行為自体が直ちに違法行為になることは、通常ありません。
しかし一方で、引き抜かれる企業にしてみれば、優秀な人材を引き抜かれるといった人的損失にとどまらず、営業秘密や個人情報が流出するおそれもありますし、競合している企業に転職した社員が従来担当していた顧客と取引を始めることによって、企業の営業に大きな影響を与えることも考えられます。
極めて背信的な方法で引き抜いた場合には違法
そこで、裁判所は、基本的に、企業間における従業員の引き抜き行為のうち単なる転職の勧誘にとどまるものは違法とはいえないが、その域を越えて社会的相当性を逸脱し極めて背信的方法で引き抜いた場合には違法となり得るという判断をしています。
例えば、東京地方裁判所・平成3年2月25日判決は、英会話教材販売会社の営業本部長が、配下のセールスマン24人を組織ごと引き抜いて、競合企業に転職させたという事例につき、引き抜いた側の企業に対し、「ある企業が競争企業の従業員に自社への転職を勧誘する場合、単なる転職の勧誘を越えて社会的相当性を逸脱した方法で従業員を引き抜いた場合には、その企業は雇用契約上の債権を侵害したものとして、不法行為として右引き抜き行為によって競争企業が受けた損害を賠償する責任がある」と判示し、引き抜いた競合企業が、企業間のセールスリクルート自粛を統一見解として明示する同業者団体に加入し、これを
また、大阪地方裁判所・平成14年9月11日判決も、労働者派遣業を営むX社の従業員であったA、Bらが、X社在職中および退職後にわたって、同業のY社と共謀しX社の派遣スタッフを大量に引き抜いたとされる事案において、上記判決と同様に、「単なる転職の勧誘の範囲を超えて社会的相当性を逸脱した方法で従業員を引き抜いた場合」には、引き抜き行為によって同業他社に生じた損害を賠償すべきとした上で、Y社は、AおよびBと共謀して、単なる転職の勧誘の範囲を超え、社会的相当性を著しく逸脱した引き抜き行為を行ったと認定し、3か月分に当たる粗利額、すなわちX社が派遣先企業から受領した売上高(派遣料)から、当該派遣スタッフに対して支給されていた、税金等の法定控除前の賃金総支給額に当該派遣スタッフにかかる各種保険料(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金等の保険料)のうちX社負担分を加えた額を控除した金額を損害として認定しています。
引き抜きにより退職しても、背景事情によっては適法に
なお、上記大阪地方裁判所の判決は、次のようにも述べています。
「一般に従業員は勤務する企業を自由に退職し、又は他企業に転職することが認められるのであるから、従業員が任意に退職又は転職することにより従前勤務していた企業に損失が生じたとしても、その企業はこれを甘受すべきものである。その企業としては、従業員を適宜補充するなどして、自助努力により損失を最小限にとどめるべきであり、これを当該従業員に負担させることはできないのであって、一時期に多数の従業員が退職又は転職した場合であっても、このことに変わりはないというべきである。仮に従業員が他の従業員や同業他社からの違法な引き抜き行為によって退職したものであっても、最終的に引き抜き行為の対象となった従業員が自由な意思に基づいて企業を退職したのであれば、これによって企業に生じた損害がすべて当該引き抜き行為と相当因果関係がある損害ということもできない」
すなわち、違法な引き抜き行為が存在し、それによって退職した場合であっても、その背景事情により、法的責任が認められない場合もあるということです。
他にも、「原告代表者の行為を原因として生じた原告の社内の混乱に嫌気がさして自発的に原告を辞めていったもの」(大阪地方裁判所・平成6年11月25日判決)、「〇〇ゼミナール(筆者注:原告が経営していた学習塾)の一部の講師が被告の計画に賛同して△△塾(筆者注:被告が開設した学習塾)に移ったと認められる」(大阪地方裁判所・平成元年12月5日判決)などと認定して、損害賠償を認めなかった判決も見受けられます。
在職中の従業員による他社への引き抜き
では、現在在籍中の従業員が、引き抜きをした場合はどうなるのでしょうか。例えば、相談のケースにおいて、会社の営業課長が、自身の退職前に、直属の優秀な部下について、自分が新たに移る会社への引き抜き行為を行っていたような場合です。
この点、裁判所は、従業員が単なる転職の勧誘をしたにとどまる場合は、雇用契約上の誠実義務に反するものではないと考えています。つまり、既に説明した他社による引き抜きの場合と同様に、単なる転職の勧誘をしたにとどまる場合は、雇用契約上の誠実義務に反するものではないが、社会的相当性を逸脱し極めて背信的方法で行われた場合には例外的に雇用契約上の誠実義務違反に該当するとし、社会的相当性を逸脱した引き抜き行為であるか否かは、諸般の事情を総合考慮して判断すべきであるとしているのです。
具体的には、前述の英会話教材販売会社の事例において、裁判所は、「およそ会社の従業員は、使用者に対して、雇用契約に付随する信義則上の義務として、就業規則を遵守するなど労働契約の債務を忠実に履行し、使用者の正当な利益を不当に侵害してはならない義務(以下「雇用契約上の誠実義務」という)を負い、従業員が右義務に違反した結果使用者に損害を与えた場合は、右損害を賠償すべき責任を負うというべきである。ところで、本件のように、企業間における従業員の引き抜き行為の是非の問題は、個人の転職の自由の保障と企業の利益の保護という二つの要請をいかに調整するかという問題でもあるが、個人の転職の自由は最大限に保障されなければならないから、従業員の引き抜き行為のうち単なる転職の勧誘に
その上で、営業本部長であるAは、X社の営業において中心的な役割を果たしていた幹部従業員で、しかも本件引き抜き行為の直前までX社の取締役でもあったうえ、その配下の部課係長及びセールスマンとともに、X社が社運をかけた企画を一切任されていたのであるから、Aとともにそれら従業員が一斉に退職すれば、X社の営業の基盤である当該企画の運営に重大な支障を生ずることは明らかで、しかもAはこれを熟知する立場にあったにもかかわらず、本件引き抜き行為に及んだ上、その方法も、まず個別的にマネジャーらに移籍を説得した上、このマネジャーらとともに、X社に知られないように内密に本件セールスマンらの移籍を計画・準備し、しかもセールスマンらが移籍を決意する以前から移籍した後の営業場所を確保したばかりか、あらかじめその営業場所に備品を運搬するなどして、移籍後直ちに営業を行うことができるように準備した後に、慰安旅行を装って、事情を知らないセールスマンらをまとめて連れ出し、本件ホテル内の一室で移籍の説得を行い、その翌日には打ち合せどおり本件ホテルに来ていた競合Y社の役員に会社の説明をしてもらい、その翌日から早速Y社の営業所で営業を始め、その後にX社への退職届を郵送させたというものであり、その態様は計画的かつ極めて背信的であったといわねばならないとして、「本件セールスマンらに対する右移籍の説得は、もはや適法な転職の勧誘に留まらず、社会的相当性を逸脱した違法な引抜行為であり、不法行為に該当すると評価せざるを得ない」と判断し、Aについて、「原告との雇用契約の誠実義務に違反したものとして、本件引き抜き行為によって原告が被った損害を賠償する義務を負うというべきてある」としています。
上記裁判所が認定したAの行為は、まるで経済小説に出てきそうな話ですが、さすがにここまでやると違法となるということです。
退職した元従業員による引き抜き
上記に対し、元従業員による引き抜き行為はどうでしょうか。相談のケースにおいて、営業課長が、退社までは何もしなかったが、退社して従業員としての地位を失った後から、社員の引き抜き行為を行うような場合です。
この場合、既に会社を離れているわけであり、雇用契約上の誠実義務は問題とならず、原則として、前述した他社による引き抜きの場合と同様に考えられます。
それに対し、就業規則などで、競業避止義務の規定が定められている場合や、当該社員から、競業避止義務を定めた誓約書の提出を受けているような場合には、引き抜き行為は競業避止義務違反として違法となる場合が出てきます。
東京地方裁判所・平成2年4月17日判決は、就業規則で退職後3年以内に限って競業避止義務を課されていた学習塾の幹部職員が、学年度途中で従業員をひきつれて退職し、その近くに新たな学習塾を開校して、講師の大半を引き抜くとともに、生徒の多くを新たな学習塾に入会させたという事例において、「年度の途中で事前に十分な余裕がないまま講師陣の大半が辞任すれば、進学塾の経営者がこれに代わるべき講師の確保に苦慮することとなり、生徒に大きな動揺を与え、相当数の生徒が該当進学塾をやめるという事態を招来しかねないというべきところ、幹部職員らの行為は、一方で会員(生徒)の教育・指導に当たっていた従業員及び講師の大半の者が、X社においてその代替要員を十分確保する時間的余裕を与えないまま一斉に退職するに至ったという事態を招来させたものであり、他方ではX社の従業員として職務を行っていた際に職務上入手した情報に基づき、会員(生徒)中約220名に対し、その住所に書面を送付してY学習塾への入会を勧誘して、125名を入会させるに至ったものであって、X社の就業規則上の競業避止義務に違反したもの」として、損害賠償請求を認めています。
場合によっては退職金の不支給や返還請求も
以上述べてきたように、社員の引き抜きについては、憲法が定めている「職業選択の自由」とも関連して、制限するのはなかなか難しいと言えるかと思います。だからこそ、藤田社長は、あえて意図的に「激怒」し、それをメディアに載せることによって、様々な批判も覚悟の上で、引き抜きの対象となる社員や、引き抜きを行おうとする他企業を
なお、引き抜きがあった場合に、当該社員に対する退職金返還請求を認めた判例がありますので、最後にご紹介したいと思います。
福井地方裁判所・昭和62年6月19日判決は、X社(新聞社)を退職した社員らが新聞発行を目的とする会社を設立し、X社から大量の労働者を引き抜くという事態が進展している中で、X社を退職し、右同業他社に就職したYらに対し、X社が、Yらの退職は退職規定中の退職金不支給事由(筆者注:X社退職一時金規定には「社の都合をかえりみず退職し、会社の業務に著しく障害を与えたとき」には退職一時金を支給しない旨の規定がある)に該当するとして、すでに支払った退職金の全額の返還を求めた事案につき、「被告ら(筆者注:Yら)の退職は本件不支給規定に該当し、被告らは、本来、退職一時金の支給を受ける地位になかったものであるにもかかわらず、真の退職理由を秘して、それぞれ退職一時金の支給を受け、原告(筆者注:X社)に右各退職一時金相当額の損失を与え、これを不当に利得したものといわざるを得ない」と判示して、退職金の返還請求を認容しています。
また、最近でも、大阪地方裁判所・平成17年11月4日判決は、多数の従業員が同業他社に転職することが組織的に実行された集団退社事件において、当該従業員らからの退職金請求につき、「原告らが……転職を勧誘することによってこの集団的な退職行為を推し進めようとした行為は、社会的に相当な範囲にとどまるものということはできず、前記の誠実義務に反する行為に当たり、原告の長年の勤続の功労を抹消してしまうほどの不信行為に当たる」として、会社による退職金の不支給を認めています。