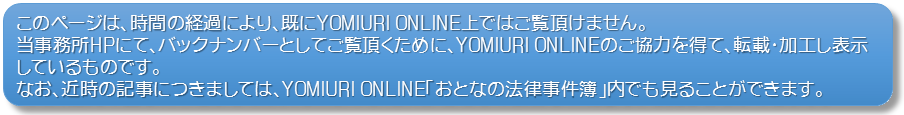支給日前に退職、ボーナスゼロに納得できない
相談者 A.Nさん
「えっ、そんなこと聞いてないわ」
書類を前に思わず声をあげてしまいました。私は29歳。7年勤めた会社を6月末に退職することになり、手続きの説明を受けている時でした。
人事部の担当者によると、うちの会社のボーナス支給日は7月20日で、支給日に会社に在籍しないと、ボーナスは1円ももらえないというのです。ボーナスの使い道まで決めていただけにショック! 「どうして?」と詰め寄っても、「会社の規定ですから」と言うばかりです。
私は学生時代から付き合っていた彼と最近結婚しました。私が退職を決めたのは、商社マンの彼がアフリカ勤務を命じられ、私もついて行くことになったからです。彼のプロポーズは突然でびっくりしたのですが、何となくズルズルと付き合いが続いていて、本当に結婚できるかどうか不安もあったので、彼の決断を促してくれた今回の転勤には感謝しているくらいです。親族と本当に親しい友人だけを招いたささやかな結婚式も無事すませ、引っ越しの準備で慌ただしい毎日ですが、海外での新生活はとても楽しみです。
会社に対しては、彼の出発に合わせて、残った有給を使い切って退社することを伝えました。今期のボーナスが1円ももらえないことは、担当者の説明を聞くまで知りませんでした。
6月末には彼と一緒にアフリカに向かうことにしており、飛行機のチケットや引っ越し荷物の発送などは全て手配済み。今さらこの日程を変更することなんてできません。
私は給与と同じように、日割りとかで支給してくれると安易に考えていたのですが、担当者からはそのような取り扱いは規則で認められていないと言われました。会社を辞める際に、給料の方はきちんと日割り計算で支給されるのに、ボーナスは支給日にいないというだけで全く支払われないのは納得いきません。私は、ボーナスの評価対象期間のほとんどをこの会社で勤務していました。出張や残業もいとわず、それなりに会社に貢献したのですから、全く会社に在籍しなかった人と同じような扱いを受けるのはどう考えてもおかしいと思います。私のように、ボーナス支給日前に退社してしまうと、ボーナスはあきらめなければならないのでしょうか。
(最近の事例をもとに創作したフィクションです)
(回答)
ボーナス減額分の半分を従業員に返還
3月5日、パナソニックが、業績不振を受けてカットしたボーナスの一部を従業員に返すことを明らかにした旨が報道され、話題になりました。同社は2013年度に従業員のボーナスを2割カットしましたが、減額分の半分を今年4月支給の給与に「経営協力感謝金」の名目で上乗せして返すということです。円安などの影響で、13年4~12月期の連結最終(当期)利益が過去最高になるなど業績が急回復していることから、従業員に還元して意欲を高めるとのことであり、総額は約100億円にも上るということです。
また、1月には、トヨタ労組が、年間のボーナスとして月給の6.8か月分(組合員1人あたりの平均で235万円超!)を要求する旨の報道が流れ、ネット上でも驚きの声が上がりました。3月4日にも、総務省が、2007年に財政破綻した北海道夕張市が2014年度から市職員のボーナスを増額することを発表するなど、近時、アベノミクスで経済が活況を呈する中で、新聞などに、「ベア満額回答」とか「ボーナス増」などの文字が躍っています。そこで今回は、ボーナスについて考えてみたいと思います。
ボーナスの意味
現在、多くの企業において、夏季及び冬季の2回、ボーナス(賞与、一時金、期末手当等の名称がありますが、本稿では、引用部分以外では「ボーナス」で統一します)が支給されています。ちなみに、厚生労働省の通達では「賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額があらかじめ確定していないものをいう」とされています。
ただ、実のところ、法律上、使用者は、従業員に対して、ボーナスを支払うのが当然とはされていません。
使用者が、ボーナスの支払い義務があるとされるのは、就業規則、賃金規程などによって支給基準が定められている場合となります。逆にいえば、就業規則、賃金規程等によって、支給基準が定められていない場合には、ボーナスを支給する、しないは使用者の裁量に委ねられているわけです。そして、ボーナスを請求する権利は、労使の交渉や使用者の決定により算定基準および算定方法が定まり、算定に必要な労働者の勤務成績の査定なども行われて初めて具体的に発生します。
従って、ボーナスを支給するという制度をそもそも置かないこともできますし、会社の業績いかんによって、たくさん支給することも、少なく支給することも可能です。
この点、ボーナスが労働基準法上の「賃金」に該当するのかという問題がありますが、上記のとおり、就業規則、賃金規程などにより、使用者にボーナスの支払いが義務付けられている場合には、ボーナスは労働基準法上の賃金ということになり、労働者は労働基準法が定める様々な保護を受けることが可能になります。
そして、ボーナスが賃金とされた場合における性質としては、過去の労働に対する報酬、(2)功労報償、(3)生活保障、(4)将来の労働意欲向上策などの意味が含まれると考えられます。そして、これらのうち、どれを重視するかによって、後に紹介する判例のように、その判断に影響を与えることになります。
年俸制の場合のボーナス
ちなみに、年俸制の場合、ボーナスが存在しない賃金支給方法(年間12等分)もありますが、夏季及び冬季のボーナス時に一定金額を支給する方法(たとえば16等分し、ボーナス時には2か月分を支給する)が比較的多く見られます。
しかしながら、前述したように、厚労省の通達では、ボーナスは、「その支給額があらかじめ確定していないものをいう」とされており、「定期的に支給されかつその支給額が確定しているものは、名称のいかんにかかわらず、これを賞与とはみなさない」としていますので、上記年俸制の場合に、夏季及び冬季といった、一般的なボーナス時に支給される金銭であっても、厳密にはボーナスではなく、確定した賃金の一部にすぎないことになります。
この場合は、ボーナスという名称であっても、前述したように、使用者は、その業績いかんによって、支給額を勝手に増減することはできません。
ボーナス支給の在籍要件
ご相談者が在籍していた企業のように、多くの企業では、ボーナスについて、支給日在籍要件、つまり、ボーナスの支給対象期間を勤務していることは当然として、さらに、ボーナスの支給日に在籍している者に支給するとの要件を定めています。この支給対象期間の満了日と支給在籍日とのズレは、1か月弱程度から、中には3か月程度という企業も存在するようです。
このように企業が支給日在籍要件を定めるのは、ボーナスには、前述のように、過去の労働に対する報酬の意味のほか、功労報償的性質や、将来の労働意欲向上といった性質があること、在籍日までの就労の確保および査定期間を確保するためと考えられています。
このような支給日在籍要件は、支給対象期間後、支給日前に退職した労働者としては、支給対象期間の労働をきちんとしているにもかかわらず、ボーナスが支給されないことになることから、果たして、この様な要件が、有効なものとして認められるのかが問題となります。
この点、かつては、無効とする裁判例もありましたが、最高裁判所は有効説の立場に立つことを明らかにしています(昭和57年10月7日判決)。
その後、例えば、東京地方裁判所の平成8年10月29日判決は、「賞与の受給資格者につき支給日現在在籍していることを要するとするいわゆる支給日在籍要件は、受給資格者を明確な基準で確定する必要から定められるものであり、十分合理性はあると認められる」「原告は、支給対象期間勤務しているにもかかわらず支給されないのは不合理である旨主張するが、賞与の前記性質及び支給日在籍要件も給与規定に明記されていることからすれば、支給対象期間経過後支給日の前日までに退職した者に不測の損害を与えるものとはいえないし、支給日在籍者と不在籍者との間に不当な差別を設けるものということもできない。したがって、支給日在籍要件を定める就業規則等の規定は労働基準法1条の趣旨等に反して無効であるとする原告の主張は採用し難い。なお、原告は、今日、賞与は労働者にとって年間所得の一部としてその生活維持のために欠くことのできない重要なものとなっている旨主張するが、仮にそのような実態があるにしても、賞与の性質等に照らして、以上の判断を左右するものではない」と明確に判示しています。
事情によっては有効性を否定した判決も
しかしながら、判例は、支給日在籍要件を常に有効としているわけではなく、具体的事情によっては、有効性を否定した例もあります。
例えば、給与規定で賞与は6月、12月に支給すると定められ、実際、例年その通り賞与の支給がされていたところ、夏季賞与の支給が3か月近く遅れて9月支給となったため、その間、退職し、支給日在籍要件から支給を受けられなくなった者について、「本来6月期に支給すべき本件賞与の支給日が、2か月以上も遅延して定められ、かつ、右遅延について宥恕(ゆうじょ=許す)すべき特段の事情のない場合についてまでも、支払日在籍者をもって支給対象者とすべき合理的理由は認められない」として、支給日在籍要件は適用されないとしています(最高裁判所・昭和60年3月12日判決、東京高等裁判所・昭和59年8月28日判決)。
従って、本件の相談者の場合も、支給日が例年よりも大幅に遅延しているなどの特別の事情があれば争うことも可能かもしれませんが、そうではなく、支給日在籍要件が就業規則等に定められており、通常通りにボーナスが支給された場合には、過去の裁判例からみても、ボーナスを支給しないという会社側の判断が有効とされる可能性が高いと考えられます。
以上のように、退職日を決めるにあたっては、就業規則や賃金規程などをよく確認した上で決定しないと、ボーナスがもらえないという思わぬ不利益を被ることがありますので注意が必要です。
支給日以降に退職を予定している者への減額は?
さて、では仮に相談者が、十分に注意をした上でボーナスがもらえるように退職日を決めた場合において、会社が、支給日以降の一定期間内に退職を予定している者と、退職が予定されていない者との間で、支給するボーナス額などについて差異を設けることは有効なのでしょうか。
東京地方裁判所の平成8年6月28日判決は、被告(退職した従業員)が、1992年(平成4年)12月14日に冬季賞与約162万2800円(基礎額の4か月分)を受領した後、その2日後(12月16日)に退職したことに対し、原告(会社)が、被告の年内退職予定を知っていれば、それを前提にして算定した賞与(年内の退職予定者であることを前提とした場合の賞与支給金額28万円)を支給したはずだと主張し、両者の計算上の差額分を、過払いとして返還請求に及んだものです。
裁判所は、将来に対する期待の程度に応じて、退職予定者と非退職予定者の賞与額に差異を設けること自体は不合理とはいえないとしつつも、具体的適用において、退職予定者は、非退職予定者の17%余のボーナスしか受領できないのは、82%余の部分の全てが将来に対する期待部分を占めることになり肯認できないとし、この82%の部分にも、本来賃金の要素からなる部分が含まれていると解さざるを得ず、従業員に対する賃金支払いを保証した労働基準法24条の趣旨に反し、民法90条の公序良俗に違反して無効と判断しました。その上で、当時の被告について、賞与額に反映させることができる範囲・割合については、これと同一の条件の非退職予定者の賞与額の20%とするのが相当であるとして、32万4560円の返還を命じています。
サイニングボーナス
なお、上記と同様に、退職とボーナスに関連した議論としては、「サイニングボーナス」の返還の問題があります。
サイニングボーナスとは、一般的に、入社後の雇用契約の成約を確認して、その後の勤労意欲の促進を目的とする金員で、労働者が会社と雇用契約を締結した際に支払われる金銭を言います。外資系企業などにおいてよく利用されていますが、その際、例えば一定期間内に自己都合で退職する場合には、会社へ返還する約定を付与しているケースがあり、問題となっています。「1年以内に自己都合退職した場合には返還する」というような約定があるということは、労働者側からすると、1年間勤務を継続しなければならなくなって、その意思に反し勤務を継続することを余儀なくされることになるからです。
裁判例では、1年以内に自発的に退職した場合には返還する旨を約束して受領した金員(200万円)について、強制労働禁止(労働基準法5条「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない」)、賠償予定の禁止(同16条「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」)に違反するとして、労働基準法13条(「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする」)および民法90条により無効としたものがあります(東京地方裁判所・平成15年3月15日判決)。
解雇や定年退職の場合は
相談者のように自主退職の場合には、退職日を自分で決定することができますが、自分で退職日を自ら選択できない解雇や定年の場合はどうなるのでしょうか。
この点、ボーナスが過去の労働に対する報酬であることを強調して、退職日を自ら選択することができる自発的退職の場合には支給日在籍要件は有効だが、会社都合による整理解雇や定年の場合には公序良俗違反で無効であり、勤務期間に応じたボーナスの請求権があるとする見解もあります。
しかし、前述の東京地方裁判所の平成8年10月29日判決は定年退職の事例であり、また、懲戒解雇の場合でも支給日在籍要件を有効と認めた裁判例もあり(東京地方裁判所・平成15年10月29日判決)、裁判例の多くは自主退職の場合と特に区別せずに支給日在籍要件を有効としています。
最後に
以上のように、ボーナスを巡っては様々な事案が想定され、多数の裁判例が存在しています。今回、ここで取りあげたもの以外にも、問題となるケースは色々とあります。
相談者が、ボーナスも給与と同じように、日割りで支給してくれると考え、ボーナスの評価対象期間のほとんどを勤務して会社業績に貢献したにもかかわらず、全く会社に在籍しなかった人と同じような取り扱いを受けるのはおかしいと思うのも無理はありませんが、残念ながら、裁判例はそのような判断を行ってはいないのです。
冒頭にご紹介したトヨタの話題を見ても、一般にボーナスを巡る話は、多額の金銭が絡んでくることが多いでしょうから、ちょっとした不注意で大きな不利益を被らないように、慎重に対応することが必要かと思います。
。