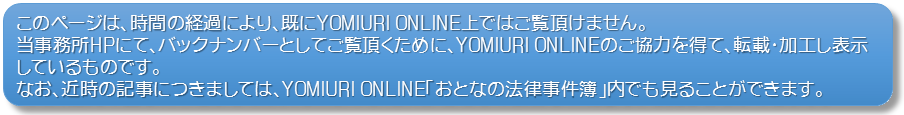TI「全財産を兄に」と亡父が遺言…1円も相続できない? TLE
相談者 K.Cさん
「大事な話があるんだ」。父の葬式が無事済んだ数日後、兄から呼ばれました。「何事だろう」と兄の会社に行ったところ、同席した会社の顧問弁護士から、父が遺言書を残していることを知らされました。
「これは公正証書遺言という正式の書類です」。弁護士は宣告するような口調で私に説明するのでした。
中身をみせてもらったところ、父の遺産のすべてを兄に渡すという内容でした。
「兄貴よぅ、1円も相続できないなんて、こんなふざけた話あるかい。絶対納得できないよ」。私は兄に食ってかかりました。
「
兄は全く動揺したそぶりも見せず、冷たく言い放ちました。部屋には父の遺影が飾ってありました。にこやかに
「血を分けた兄弟にこんな仕打ちをするなんて、俺は絶対に許せない。訴えてやるからな」。私は捨て
私の父は、若いころに裸一貫で会社を立ち上げ、小さいながらも、業界ではそれなりに名前の知れた会社にまで成長させました。父は仕事一筋で、私は小さいころから、土曜・日曜になると、会社の工場の一角で遊んでいたのを覚えています。
兄は大学を卒業した後、他の会社に就職しましたが、何年かして退職し、父の会社に入りました。父が会長、兄が社長として、実質的な仕事はすべて兄が取り仕切る形になり、会社の業績はそれなりに順調でした。
仕事しか頭にない私の父を支え続けてきた母は、5年前に亡くなり、それを機に兄夫婦が実家に同居するようになり、父の面倒を見てきました。そんな父も、母を亡くしたことをきっかけにだんだん弱ってきて、今年の春に亡くなりました。
私はというと、仕事一筋の父とは何となく折り合いが悪く、社会に出てからは、ほとんど実家には行くことはありませんでした。アルバイト収入や、母が父に内緒でこっそりと送ってくれる仕送りなどで、勝手気ままに暮らしてきました。母が亡くなった後は、兄が援助してくれました。「兄は俺のことを気にかけてくれている」と信じていただけに、今回の兄の仕打ちは許せません。
好き勝手に暮らしてきた私と違い、父の会社をちゃんと継いで、また父が弱った後の面倒を見てくれた兄が多くの財産を承継するのは理解できます。でも、自分の取り分が全くないというのが納得できないのです。ネットで調べたら、遺留分というものがあり、「相続人は最低限の取り分を確保できる」とありました。どのようにすれば良いか教えていただけますでしょうか。(最近の事例を参考に創作したフィクションです)。
遺産を誰に渡そうと本来自由
遺言とは、自分が生涯をかけて築いてきた、あるいは先祖から引き継いできた大切な財産(遺産)に関わる、遺言者(被相続人)の意思表示であり、その最も重要な機能は、遺産の処分に関して、「遺言者(被相続人)の意思」を反映させることにあります。つまり、遺言のある場合は、遺言に書かれている遺言者の意思に基づいて、遺産が分配されることになります。
本件のように、家業である会社を承継し親の面倒を見てくれていた子供(兄)と、ほとんど実家には行くことはなく気ままに暮らしてきた子供(相談者)がいる場合、親が前者に財産を全て渡す旨の遺言書を残すことは、相談者には申し訳ありませんが、人間の感情として理解でき、そういった感情(意思)を遺産の分配にきちんと反映させることこそが、まさに遺言書の重要な機能となるわけです。
つまり、遺言者は、遺言によって、自己の財産を自由に処分することができるのが原則なのであり、家族に対しては1円も与えず、生前に応援してきた福祉団体等に寄付したり、それこそ赤の他人に全ての財産を与えるのも自由です。同様に、本件のように、2人の子供のうち、兄にだけ財産を全て与え、弟には1円も渡さないのも本来自由ということです。
他方、仮に遺言を残さないで亡くなった場合には、遺言者が生前有していた意思に関わりなく、あらかじめ遺産の分配について規定している民法に従って形式的に相続が行われることとなります。つまり、配偶者と子供が相続人である場合、死亡した人の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の人は一定の順位に従って配偶者と一緒に相続人になり、第1順位が「死亡した人の子供」で、配偶者2分の1、子供2分の1で分け合うことになります。子供が2人以上いる場合は、原則として均等に分けられますから、本件の場合は、お母さんが既に亡くなっていますので、兄と弟で2分の1ずつ遺産を取得する事になります。
ちなみに、本連載「遺言書がないと、遺された妻は亡き夫の兄弟に財産を奪われる?」(2012年4月11日)で説明したように、子供がいない夫婦の場合は、第2順位の「死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)」が配偶者と共に相続し(配偶者が3分の2、父母らが3分の1)、また直系尊属もいない場合は、第3順位の「死亡した人の兄弟姉妹」が相続することになります(配偶者が4分の3、兄弟姉妹らが4分の1)。
たとえ常日ごろ、自分の親から、死亡後の財産の処分方法について詳細な説明がなされていたとしても、それがきちんと遺言書の形になっていない限り、民法の規定によって具体的な事情など基本的に無視され、上記のような法律に定められた割合に従い、形式的に遺産の分配が決定されてしまうことになります。
相続で争いになると、必ずといってよいほど、「父はこの家を私にくれるといつも言っていた」などと主張する人が出てきますが、それがきちんと遺言書の形で文書として残されていなければ、法的に意味などないわけです。仮に、お父さんが本当にそのように考えていてそれを実現したいのなら、その意思を記した、適式な遺言書を残しておかなければならないということです。
遺留分制度はなぜ存在?
遺留分は、相続にまつわる紛争について説明する際には必ず出て来る概念であり、本連載でも過去に何度か取りあげてきました。この制度は、遺産の最低限度の取り分として遺産の一定割合の取得を法が保障したものであり、それに反する内容の遺言書があっても、法定相続人はその最低限の財産を取得できるようになっているものです。
前記のように、遺言者は、遺言によって、自己の財産を自由に処分することができるのが原則です。しかし、相続という制度は、遺族の生活保障や遺産形成に貢献した遺族の潜在的持ち分の清算等の機能も有していると考えられています。そのため、民法は、「遺留分制度」という、被相続人が有していた相続財産について、その「一定の割合」の承継を、一定の法定相続人に対して保障する制度を設けて、「遺言者(被相続人)の遺産処分の自由」と「相続人の保護」という、相反する要請の調整を図っているわけです。
確かに、赤の他人に財産をすべて渡すなどという遺言がなされ、それがそのまま実行されるとすれば、残された家族はたまったものではありません。長年連れ添ってきた奥さんがいるにも関わらず「財産は全て愛人にわたす」といった遺言がなされて、その通りになるとすれば、奥さんはその後の生活に困ってしまいます。奥さんの生活がある程度保証される必要があることはもちろんですし、そもそも、奥さんの貢献があったからこそ、夫は一定の財産を形成できたとも評価できるのであり、その貢献分を奥さんが確保するのは当然とも言えます。この点について異論を述べる人はおそらく余りいないでしょう。
ただ、他方で、例えば、長年の間、肉体的もしくは精神的に親に虐待を加えてきた子供に対して1円も渡したくないという場合などを想定すると、状況が変わってきます。
相続に関連したネット上のブログなどを見てみると、それは当然の感情であって責められる方が間違いとして、遺言書に優先する遺留分の制度に疑問を呈する意見なども見られます。ちなみに、このような場合に備えて、本連載「借金の尻ぬぐいで『勘当』した息子、相続から除外できる?」(2012年8月22日)でご紹介した「廃除」という制度が存在します。ただ、客観的かつ社会通念に照らし、推定相続人の遺留分を否定することが正当であると判断される程度に重大な事由がなければならないとされており、簡単に利用できる制度ではないことも、こういった意見に拍車をかけることになります。
さて、以上のような制度状況を前提として、実際の裁判などを見てみると、遺留分が問題となるのは、前者のケースのような極端な場合ではなく、複数の子供がいる場合に、遺言書で不均衡な遺産の配分が指示された場合が多いのが現実です。
遺留分の具体的内容
遺留分減殺請求権で法定分を獲得
民法で遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子、直系尊属とされており、子の代襲相続人も、被代襲者である子と同じ遺留分を持つこととされていますが、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。この点は、本連載「遺言書がないと、遺された妻は亡き夫の兄弟に財産を奪われる?」(2012年4月11日)の解説をご参照いただきたいと思いますが、だからこそ、この場合は遺言書を必ず遺しておく必要があるわけです。ちなみに、直系尊属(父母や祖父母など)が相続人となる場合には遺留分が存在しますので、子供のいない夫婦の場合で、配偶者に全ての財産をわたすと書かれた遺言書があった場合でも、その父母は、遺留分を主張することができることになります。
本件において、相談者は、被相続人であるお父さんの子供に該当しますので、当然に遺留分が認められています。そして、上記のように、遺留分は、遺産全体に対する割合として規定されているわけですが、子供の場合は、通常の相続分の2分の1が遺留分となり、相談者とお兄さんの2人が相続人であることから、本件相談者の遺留分は、さらに、法定相続分の2分の1を乗じることとなり、全体の遺産の4分の1となるわけです。したがって、相談者は、お兄さんに対して、後述する遺留分減殺請求権を行使して、全体の遺産の4分の1を獲得することができます。
明確な権利行使が必要
民法では、遺留分を侵害する行為が当然に無効とされるのではなく、遺留分を侵害された法定相続人に対して、「遺留分減殺請求権」を行使する必要があります。つまり、相続人は、遺留分減殺請求権を行使しないこともできますし、遺留分を放棄することもできます。
最高裁判所も、「遺留分制度は、被相続人の財産処分の自由と身分関係を背景とした相続人の諸利益との調整を図るものである。民法は、被相続人の財産処分の自由を尊重して、遺留分を侵害する遺言について、いったんその意思どおりの効果を生じさせるものとした上、これを覆して侵害された遺留分を回復するかどうかを、専ら遺留分権利者の自律的決定にゆだねたものということができる。」(平成13年11月22日判決)と判示しています。
したがって、遺留分を侵害する遺言書が作成されていても、相続人が、正式に遺留分減殺請求をしない限り、遺言とおりに、遺産が分配されることとなってしまいます。
本件の相談者も、お父さんの遺産を全てお兄さんが相続することに異議があるのであれば、遺留分減殺請求権を行使する必要があります。
なお、遺留分減殺請求権は、必ずしも訴えの方法によることを要せず、相手方に対する意思表示によって行えば足ります。ただ、この意思表示は、いつまでもできるわけではなく、相続開始(及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったこと)を知ったときから1年または相続開始のときから10年を経過したときには行う事ができなくなります。
口頭で遺留分減殺請求権を行使したと幾ら主張しても、相手方がそんなことは聞いていないと反論した際には、権利行使の有無自体が紛争となってしまい、「言った、言わない」という争いになれば、通常は、なぜそんな重要なことを口頭でのみ行って書面に残さなかったのかということになるのであって、口頭での権利行使が認められない結果に終わることが多いので、そのような不毛な争いを避けるためにも、必ず証拠に残る形で、つまり通常は「配達証明付内容証明郵便」によって行われることになります。
なお、本件相談では、相続人が相談者とお兄さんの2人しかいないようなので問題になりませんが、仮に他にも何人も相続人がいる場合、基本的に、自分以外の相続人すべてに対して、念のために意思表示を行っておくことがよろしいかと思います。例えば、兄弟が3人いて、うち1人だけが相続によって多額の財産をもらったと思って、その1人にだけ遺留分減殺請求の意思表示をしていたところ、実はもう1人の兄弟がもらっていた財産の方が多額であったというような事態が往々にして発生するからです。
具体的な遺留分の算定
遺留分算定の基礎となる財産額は、相続開始時に被相続人が有した財産の価額に、被相続人が贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して算定されます。被相続人が贈与した財産の価額を加算するのは、加算しないと、被相続人が死亡する直前に所有していた多額の財産を他人に贈与していたような場合に、遺留分制度の目的が達成できなくなるからです。
加算される贈与は、<1>相続開始前の1年間にされた贈与<2>遺留分減殺請求権を有する者に損害を加えることを知ってした贈与<3>不相当な対価でなされた贈与――などに限定されています。
本件の場合にも、このような贈与が、被相続人であるお父さんからお兄さんに対して既になされていた場合には、遺留分算定の基礎となる財産額に加算されることとなります。
いずれにしても、相談者は、お兄さんに対して遺留分減殺請求権を行使すれば、全体の相続財産の4分の1を取得することができることになります。この算定方法等は、複雑で難しい話になりますので、この程度にとどめておきたいと思います。
お兄さんの功労分は?
同居だけでは難しい「寄与分」
さて、本件の場合、相談者も認めているとおり、お兄さんがお父さんの会社を手伝い、また、同居してお父さんの面倒を見てきたという事実があります。そして、遺産分割にあたっては、共同相続人のうち被相続人の財産の維持または増加について特別に寄与した者には、法定相続分の他に「寄与分」が認められ、他の共同相続人よりも多く遺産分割を受けられます。相続人である複数の子どものうち1人が親と同居して長年介護してきたとか、親の家業を手伝ってきたというような場合が典型例です。ただ、単に同居して親の面倒を見てきたという程度では、寄与分はなかなか認められないのが実情です。まさに、「特別に」寄与したことが必要なわけです。
たとえば、大阪家庭裁判所堺支部平成18年3月22日審判では、「相手方Aは、…被相続人の入院時の世話をし、また、通院の付き添いをしていたものであるが、これは同居している親族の相互扶助の範囲を超えるものであるとはいえない上、これによって、被相続人が特別にその財産の減少を免れたことを認めるに足りる資料は見当たらない。そうすると、これをもって、相手方Aに被相続人の財産の維持につき特別の寄与があったとみることはできない。」などと判示しています。
さて、本件の場合、お父さんの面倒を見てきたという事実以外に、お父さんの会社を手伝ったという事実があり、上記の判示にもある「被相続人が特別にその財産の減少を免れたこと」という事情が認められる可能性が高いと思われます。現に、寄与分を認められる例としては、親の家業を手伝ったという事例が多いのです。
では、この寄与分について、遺留分とはどの様な関係にあるのでしょうか。つまり、前述のように、遺留分算定の基礎となる財産額は、相続開始時に被相続人が有した財産の価額に、被相続人が贈与した財産の価額を加えて算定されるわけですが、上記のような寄与分を控除する必要はないのかという疑問です。この点の帰趨きすうにより、本件の場合、お兄さんが、自らの寄与分を主張してきた場合に、相談者の遺留分に影響が出る可能性があるわけです。
この点、裁判例では、遺留分減殺請求訴訟において、寄与者は寄与の事実を抗弁として主張して減殺額の減少を主張することはできないとされています。したがって、相談者がお兄さんに遺留分減殺請求権を行使した場合、お兄さんが寄与分を主張したとしても、相談者の遺留分には影響はないこととなります。
なお、これは一件不合理なようにも見えますが、法理論は別として、実質的に見ると、特別の寄与をしたからこそ、お兄さんはお父さん(被相続人)から多くの財産を受け取ることになったとも考えられるので問題はないなどとも言われています。
お兄さんとよく相談して解決を
さて、以上説明したように、相談者としては、遺留分減殺請求権を行使することにより、全体の遺産の4分の1を取得することができるわけですが、権利行使したからといって、直ちに遺産の一部を手に入れられるわけではありません。相続財産が全て現金なら、その4分の1を算定するのは簡単ですが、通常は、土地、建物、株式、絵画等、様々な財産を含んでいることが多いのであり、その評価をしなければ4分の1がどの程度になるかはっきりしないからです。
そして、当事者同士で協議がまとまらないと、通常は、家庭裁判所における調停の手続きの中で協議することになります。調停とは、裁判所における、裁判官等を交えた話し合いと思っていただければ良いと思います。費用も手間もかかりますし、調停がまとまらなければ、裁判という最終的な手続きに進むことになり、兄弟の間には修復できないほど決定的な亀裂ができることになります。私も、仲の良かった兄弟が、家庭裁判所の廊下でつかみ合いの喧嘩けんかになりそうな場面を幾度か目撃したことがありますが、それは決して、ご両親の望むものではないと思いますし、お兄さんもそのような事態を望んではいないと思います。
本件では、お兄さんは、お母さんが亡くなった後、相談者を援助してくれたということであり、決して、相談者を見捨てているという訳ではなさそうです。
本件のように、お兄さんが家業を継いでいるような場合、会社の運転資金確保や銀行からの融資等の関係で、会社承継者に遺産を集中させなければならない事情もよく見受けられます。現にお兄さんも「財産分けで親父が苦労して作った会社を傾けるわけにはいかない」と言っています。その点、お父さんがなぜこのような遺言書を残したかも含めて、お兄さんとよく話し合われて、裁判所が関与するまでもなく、お互いに納得できる解決を図る努力をすることをお勧めしたいと思います。
元の記事を読む
http://www.yomiuri.co.jp/life/hobby/law/20150612-OYT8T50330.html#csidx5e20901eaa7902fb3793687002b7683
Copyright © The Yomiuri Shimbun
「大事な話があるんだ」。父の葬式が無事済んだ数日後、兄から呼ばれました。「何事だろう」と兄の会社に行ったところ、同席した会社の顧問弁護士から、父が遺言書を残していることを知らされました。
「これは公正証書遺言という正式の書類です」。弁護士は宣告するような口調で私に説明するのでした。
中身をみせてもらったところ、父の遺産のすべてを兄に渡すという内容でした。
「兄貴よぅ、1円も相続できないなんて、こんなふざけた話あるかい。絶対納得できないよ」。私は兄に食ってかかりました。
「
兄は全く動揺したそぶりも見せず、冷たく言い放ちました。部屋には父の遺影が飾ってありました。にこやかに
「血を分けた兄弟にこんな仕打ちをするなんて、俺は絶対に許せない。訴えてやるからな」。私は捨て
私の父は、若いころに裸一貫で会社を立ち上げ、小さいながらも、業界ではそれなりに名前の知れた会社にまで成長させました。父は仕事一筋で、私は小さいころから、土曜・日曜になると、会社の工場の一角で遊んでいたのを覚えています。
兄は大学を卒業した後、他の会社に就職しましたが、何年かして退職し、父の会社に入りました。父が会長、兄が社長として、実質的な仕事はすべて兄が取り仕切る形になり、会社の業績はそれなりに順調でした。
仕事しか頭にない私の父を支え続けてきた母は、5年前に亡くなり、それを機に兄夫婦が実家に同居するようになり、父の面倒を見てきました。そんな父も、母を亡くしたことをきっかけにだんだん弱ってきて、今年の春に亡くなりました。
私はというと、仕事一筋の父とは何となく折り合いが悪く、社会に出てからは、ほとんど実家には行くことはありませんでした。アルバイト収入や、母が父に内緒でこっそりと送ってくれる仕送りなどで、勝手気ままに暮らしてきました。母が亡くなった後は、兄が援助してくれました。「兄は俺のことを気にかけてくれている」と信じていただけに、今回の兄の仕打ちは許せません。
好き勝手に暮らしてきた私と違い、父の会社をちゃんと継いで、また父が弱った後の面倒を見てくれた兄が多くの財産を承継するのは理解できます。でも、自分の取り分が全くないというのが納得できないのです。ネットで調べたら、遺留分というものがあり、「相続人は最低限の取り分を確保できる」とありました。どのようにすれば良いか教えていただけますでしょうか。(最近の事例を参考に創作したフィクションです)。
遺産を誰に渡そうと本来自由
遺言とは、自分が生涯をかけて築いてきた、あるいは先祖から引き継いできた大切な財産(遺産)に関わる、遺言者(被相続人)の意思表示であり、その最も重要な機能は、遺産の処分に関して、「遺言者(被相続人)の意思」を反映させることにあります。つまり、遺言のある場合は、遺言に書かれている遺言者の意思に基づいて、遺産が分配されることになります。
本件のように、家業である会社を承継し親の面倒を見てくれていた子供(兄)と、ほとんど実家には行くことはなく気ままに暮らしてきた子供(相談者)がいる場合、親が前者に財産を全て渡す旨の遺言書を残すことは、相談者には申し訳ありませんが、人間の感情として理解でき、そういった感情(意思)を遺産の分配にきちんと反映させることこそが、まさに遺言書の重要な機能となるわけです。
つまり、遺言者は、遺言によって、自己の財産を自由に処分することができるのが原則なのであり、家族に対しては1円も与えず、生前に応援してきた福祉団体等に寄付したり、それこそ赤の他人に全ての財産を与えるのも自由です。同様に、本件のように、2人の子供のうち、兄にだけ財産を全て与え、弟には1円も渡さないのも本来自由ということです。
他方、仮に遺言を残さないで亡くなった場合には、遺言者が生前有していた意思に関わりなく、あらかじめ遺産の分配について規定している民法に従って形式的に相続が行われることとなります。つまり、配偶者と子供が相続人である場合、死亡した人の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の人は一定の順位に従って配偶者と一緒に相続人になり、第1順位が「死亡した人の子供」で、配偶者2分の1、子供2分の1で分け合うことになります。子供が2人以上いる場合は、原則として均等に分けられますから、本件の場合は、お母さんが既に亡くなっていますので、兄と弟で2分の1ずつ遺産を取得する事になります。
ちなみに、本連載「遺言書がないと、遺された妻は亡き夫の兄弟に財産を奪われる?」(2012年4月11日)で説明したように、子供がいない夫婦の場合は、第2順位の「死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)」が配偶者と共に相続し(配偶者が3分の2、父母らが3分の1)、また直系尊属もいない場合は、第3順位の「死亡した人の兄弟姉妹」が相続することになります(配偶者が4分の3、兄弟姉妹らが4分の1)。
たとえ常日ごろ、自分の親から、死亡後の財産の処分方法について詳細な説明がなされていたとしても、それがきちんと遺言書の形になっていない限り、民法の規定によって具体的な事情など基本的に無視され、上記のような法律に定められた割合に従い、形式的に遺産の分配が決定されてしまうことになります。
相続で争いになると、必ずといってよいほど、「父はこの家を私にくれるといつも言っていた」などと主張する人が出てきますが、それがきちんと遺言書の形で文書として残されていなければ、法的に意味などないわけです。仮に、お父さんが本当にそのように考えていてそれを実現したいのなら、その意思を記した、適式な遺言書を残しておかなければならないということです。
遺留分制度はなぜ存在?
遺留分は、相続にまつわる紛争について説明する際には必ず出て来る概念であり、本連載でも過去に何度か取りあげてきました。この制度は、遺産の最低限度の取り分として遺産の一定割合の取得を法が保障したものであり、それに反する内容の遺言書があっても、法定相続人はその最低限の財産を取得できるようになっているものです。
前記のように、遺言者は、遺言によって、自己の財産を自由に処分することができるのが原則です。しかし、相続という制度は、遺族の生活保障や遺産形成に貢献した遺族の潜在的持ち分の清算等の機能も有していると考えられています。そのため、民法は、「遺留分制度」という、被相続人が有していた相続財産について、その「一定の割合」の承継を、一定の法定相続人に対して保障する制度を設けて、「遺言者(被相続人)の遺産処分の自由」と「相続人の保護」という、相反する要請の調整を図っているわけです。
確かに、赤の他人に財産をすべて渡すなどという遺言がなされ、それがそのまま実行されるとすれば、残された家族はたまったものではありません。長年連れ添ってきた奥さんがいるにも関わらず「財産は全て愛人にわたす」といった遺言がなされて、その通りになるとすれば、奥さんはその後の生活に困ってしまいます。奥さんの生活がある程度保証される必要があることはもちろんですし、そもそも、奥さんの貢献があったからこそ、夫は一定の財産を形成できたとも評価できるのであり、その貢献分を奥さんが確保するのは当然とも言えます。この点について異論を述べる人はおそらく余りいないでしょう。
ただ、他方で、例えば、長年の間、肉体的もしくは精神的に親に虐待を加えてきた子供に対して1円も渡したくないという場合などを想定すると、状況が変わってきます。
相続に関連したネット上のブログなどを見てみると、それは当然の感情であって責められる方が間違いとして、遺言書に優先する遺留分の制度に疑問を呈する意見なども見られます。ちなみに、このような場合に備えて、本連載「借金の尻ぬぐいで『勘当』した息子、相続から除外できる?」(2012年8月22日)でご紹介した「廃除」という制度が存在します。ただ、客観的かつ社会通念に照らし、推定相続人の遺留分を否定することが正当であると判断される程度に重大な事由がなければならないとされており、簡単に利用できる制度ではないことも、こういった意見に拍車をかけることになります。
さて、以上のような制度状況を前提として、実際の裁判などを見てみると、遺留分が問題となるのは、前者のケースのような極端な場合ではなく、複数の子供がいる場合に、遺言書で不均衡な遺産の配分が指示された場合が多いのが現実です。
遺留分の具体的内容
遺留分減殺請求権で法定分を獲得
民法で遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子、直系尊属とされており、子の代襲相続人も、被代襲者である子と同じ遺留分を持つこととされていますが、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。この点は、本連載「遺言書がないと、遺された妻は亡き夫の兄弟に財産を奪われる?」(2012年4月11日)の解説をご参照いただきたいと思いますが、だからこそ、この場合は遺言書を必ず遺しておく必要があるわけです。ちなみに、直系尊属(父母や祖父母など)が相続人となる場合には遺留分が存在しますので、子供のいない夫婦の場合で、配偶者に全ての財産をわたすと書かれた遺言書があった場合でも、その父母は、遺留分を主張することができることになります。
本件において、相談者は、被相続人であるお父さんの子供に該当しますので、当然に遺留分が認められています。そして、上記のように、遺留分は、遺産全体に対する割合として規定されているわけですが、子供の場合は、通常の相続分の2分の1が遺留分となり、相談者とお兄さんの2人が相続人であることから、本件相談者の遺留分は、さらに、法定相続分の2分の1を乗じることとなり、全体の遺産の4分の1となるわけです。したがって、相談者は、お兄さんに対して、後述する遺留分減殺請求権を行使して、全体の遺産の4分の1を獲得することができます。
明確な権利行使が必要
民法では、遺留分を侵害する行為が当然に無効とされるのではなく、遺留分を侵害された法定相続人に対して、「遺留分減殺請求権」を行使する必要があります。つまり、相続人は、遺留分減殺請求権を行使しないこともできますし、遺留分を放棄することもできます。
最高裁判所も、「遺留分制度は、被相続人の財産処分の自由と身分関係を背景とした相続人の諸利益との調整を図るものである。民法は、被相続人の財産処分の自由を尊重して、遺留分を侵害する遺言について、いったんその意思どおりの効果を生じさせるものとした上、これを覆して侵害された遺留分を回復するかどうかを、専ら遺留分権利者の自律的決定にゆだねたものということができる。」(平成13年11月22日判決)と判示しています。
したがって、遺留分を侵害する遺言書が作成されていても、相続人が、正式に遺留分減殺請求をしない限り、遺言とおりに、遺産が分配されることとなってしまいます。
本件の相談者も、お父さんの遺産を全てお兄さんが相続することに異議があるのであれば、遺留分減殺請求権を行使する必要があります。
なお、遺留分減殺請求権は、必ずしも訴えの方法によることを要せず、相手方に対する意思表示によって行えば足ります。ただ、この意思表示は、いつまでもできるわけではなく、相続開始(及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったこと)を知ったときから1年または相続開始のときから10年を経過したときには行う事ができなくなります。
口頭で遺留分減殺請求権を行使したと幾ら主張しても、相手方がそんなことは聞いていないと反論した際には、権利行使の有無自体が紛争となってしまい、「言った、言わない」という争いになれば、通常は、なぜそんな重要なことを口頭でのみ行って書面に残さなかったのかということになるのであって、口頭での権利行使が認められない結果に終わることが多いので、そのような不毛な争いを避けるためにも、必ず証拠に残る形で、つまり通常は「配達証明付内容証明郵便」によって行われることになります。
なお、本件相談では、相続人が相談者とお兄さんの2人しかいないようなので問題になりませんが、仮に他にも何人も相続人がいる場合、基本的に、自分以外の相続人すべてに対して、念のために意思表示を行っておくことがよろしいかと思います。例えば、兄弟が3人いて、うち1人だけが相続によって多額の財産をもらったと思って、その1人にだけ遺留分減殺請求の意思表示をしていたところ、実はもう1人の兄弟がもらっていた財産の方が多額であったというような事態が往々にして発生するからです。
具体的な遺留分の算定
遺留分算定の基礎となる財産額は、相続開始時に被相続人が有した財産の価額に、被相続人が贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して算定されます。被相続人が贈与した財産の価額を加算するのは、加算しないと、被相続人が死亡する直前に所有していた多額の財産を他人に贈与していたような場合に、遺留分制度の目的が達成できなくなるからです。
加算される贈与は、<1>相続開始前の1年間にされた贈与<2>遺留分減殺請求権を有する者に損害を加えることを知ってした贈与<3>不相当な対価でなされた贈与――などに限定されています。
本件の場合にも、このような贈与が、被相続人であるお父さんからお兄さんに対して既になされていた場合には、遺留分算定の基礎となる財産額に加算されることとなります。
いずれにしても、相談者は、お兄さんに対して遺留分減殺請求権を行使すれば、全体の相続財産の4分の1を取得することができることになります。この算定方法等は、複雑で難しい話になりますので、この程度にとどめておきたいと思います。
お兄さんの功労分は?
同居だけでは難しい「寄与分」
さて、本件の場合、相談者も認めているとおり、お兄さんがお父さんの会社を手伝い、また、同居してお父さんの面倒を見てきたという事実があります。そして、遺産分割にあたっては、共同相続人のうち被相続人の財産の維持または増加について特別に寄与した者には、法定相続分の他に「寄与分」が認められ、他の共同相続人よりも多く遺産分割を受けられます。相続人である複数の子どものうち1人が親と同居して長年介護してきたとか、親の家業を手伝ってきたというような場合が典型例です。ただ、単に同居して親の面倒を見てきたという程度では、寄与分はなかなか認められないのが実情です。まさに、「特別に」寄与したことが必要なわけです。
たとえば、大阪家庭裁判所堺支部平成18年3月22日審判では、「相手方Aは、…被相続人の入院時の世話をし、また、通院の付き添いをしていたものであるが、これは同居している親族の相互扶助の範囲を超えるものであるとはいえない上、これによって、被相続人が特別にその財産の減少を免れたことを認めるに足りる資料は見当たらない。そうすると、これをもって、相手方Aに被相続人の財産の維持につき特別の寄与があったとみることはできない。」などと判示しています。
さて、本件の場合、お父さんの面倒を見てきたという事実以外に、お父さんの会社を手伝ったという事実があり、上記の判示にもある「被相続人が特別にその財産の減少を免れたこと」という事情が認められる可能性が高いと思われます。現に、寄与分を認められる例としては、親の家業を手伝ったという事例が多いのです。
では、この寄与分について、遺留分とはどの様な関係にあるのでしょうか。つまり、前述のように、遺留分算定の基礎となる財産額は、相続開始時に被相続人が有した財産の価額に、被相続人が贈与した財産の価額を加えて算定されるわけですが、上記のような寄与分を控除する必要はないのかという疑問です。この点の帰趨きすうにより、本件の場合、お兄さんが、自らの寄与分を主張してきた場合に、相談者の遺留分に影響が出る可能性があるわけです。
この点、裁判例では、遺留分減殺請求訴訟において、寄与者は寄与の事実を抗弁として主張して減殺額の減少を主張することはできないとされています。したがって、相談者がお兄さんに遺留分減殺請求権を行使した場合、お兄さんが寄与分を主張したとしても、相談者の遺留分には影響はないこととなります。
なお、これは一件不合理なようにも見えますが、法理論は別として、実質的に見ると、特別の寄与をしたからこそ、お兄さんはお父さん(被相続人)から多くの財産を受け取ることになったとも考えられるので問題はないなどとも言われています。
お兄さんとよく相談して解決を
さて、以上説明したように、相談者としては、遺留分減殺請求権を行使することにより、全体の遺産の4分の1を取得することができるわけですが、権利行使したからといって、直ちに遺産の一部を手に入れられるわけではありません。相続財産が全て現金なら、その4分の1を算定するのは簡単ですが、通常は、土地、建物、株式、絵画等、様々な財産を含んでいることが多いのであり、その評価をしなければ4分の1がどの程度になるかはっきりしないからです。
そして、当事者同士で協議がまとまらないと、通常は、家庭裁判所における調停の手続きの中で協議することになります。調停とは、裁判所における、裁判官等を交えた話し合いと思っていただければ良いと思います。費用も手間もかかりますし、調停がまとまらなければ、裁判という最終的な手続きに進むことになり、兄弟の間には修復できないほど決定的な亀裂ができることになります。私も、仲の良かった兄弟が、家庭裁判所の廊下でつかみ合いの喧嘩けんかになりそうな場面を幾度か目撃したことがありますが、それは決して、ご両親の望むものではないと思いますし、お兄さんもそのような事態を望んではいないと思います。
本件では、お兄さんは、お母さんが亡くなった後、相談者を援助してくれたということであり、決して、相談者を見捨てているという訳ではなさそうです。
本件のように、お兄さんが家業を継いでいるような場合、会社の運転資金確保や銀行からの融資等の関係で、会社承継者に遺産を集中させなければならない事情もよく見受けられます。現にお兄さんも「財産分けで親父が苦労して作った会社を傾けるわけにはいかない」と言っています。その点、お父さんがなぜこのような遺言書を残したかも含めて、お兄さんとよく話し合われて、裁判所が関与するまでもなく、お互いに納得できる解決を図る努力をすることをお勧めしたいと思います。