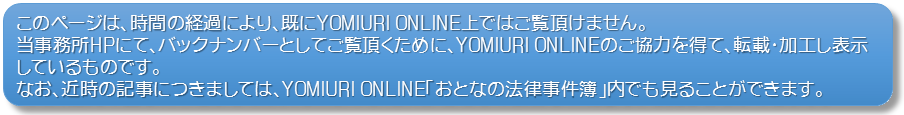裁判で懲役刑の年数はどうやって決まるの?
相談者 I.Nさん
私は相次ぐ児童虐待事件に胸を痛め、数年前から母親が集うサロンを開いています。
子育てに追われるママたちに息抜きの場を提供し、育児の悩みを自由に打ち明けられるようにするためです。そんな私がつい最近、新聞を読んでいて「こんなのありえないわ」と思わず叫んでしまう記事に出くわしました。
その記事は、両親が子どもを虐待死させたという傷害致死事件を扱ったもので、裁判員裁判で懲役15年という重い判決が出たのに、最高裁判所が、それを覆してより軽い刑にしたと書いてありました。最高裁判所は、過去の裁判結果との公平性を保つ必要性があると考えてこのような判断を下したとのことですが、一般市民の感覚を裁判に反映させることが目的の裁判員裁判なのに、このようなことが行われたのでは、意味がないのではないかと思いました。紙面には「ほかの傷害致死事件とは悪質性がまるで違うのに、過去の量刑傾向に合わせた判決になるのは残念でならない」との、裁判員の方のコメントも載っていました。
この事件は、極めて悪質な児童虐待で子どもを死なせた事案なので、過去の例に比べて重い刑が言い渡されても何らおかしくはないはずです。私はサロンでみんなの意見を聞いてみましたが、「子どもを虐待死させた親には重い罰を科すべきだ」という意見が大勢を占めました。これが世間一般の感覚ではないでしょうか。私には法律の世界のことはよくわかりません。そこでお聞きしたいのが、刑事事件での懲役刑の年数がどのような基準で決まるかという点です。人を1人殺したら何年、お金をいくら盗んだら何年などというように、何か基準があるのでしょうか。そして、その基準は私たちの市民感覚よりも重視されるべきものなのでしょうか。(最近の事例をもとに創作したフィクションです)
(回答)
求刑超え裁判員判決の破棄
今年7月25日、新聞に「求刑超え裁判員判決 破棄」「求刑1.5倍判決を破棄」といった見出しが躍りました。幼児を虐待したとして傷害致死罪に問われた両親に対し、求刑の1.5倍の懲役15年の判決を言い渡した裁判員裁判の量刑判断の是非が問われた事件の上告審で、最高裁判所が、刑事裁判に国民の視点を入れるために導入された裁判員裁判といえども「他の裁判の結果との公平性が保持された適正なものでなければならない」との初の判断を示したからです。結局、1審、2審の判決は破棄され、父親を懲役10年、母親を同8年と、原審から大幅に軽減する判決が言い渡されました。いずれも同種事犯に対する過去の判決結果と同水準の刑に落ち着いたわけです。これは最高裁判所の判断ですから、この判決によって、この2人の刑は確定したことになります。
しかし、裁判員裁判は、本来、市民の日常感覚や常識を裁判に反映させるとの趣旨で導入された制度であり、その趣旨を考えると、ある意味、従来の刑と
そこで、今回は、新聞などでよく見る、「懲役10年」といった刑が、どの様な手順で導かれるのかという、刑事裁判における量刑の問題について説明してみたいと思います。
刑事裁判における量刑とは
裁判所は、適用すべき刑罰法規の定める「法定刑」につき、刑法を適用して定まる処断刑の範囲内で、自らの裁量によって刑の種類とその量を決定し、被告人に宣告することとなります。この過程を「量刑」とか「刑の量定」といいます。
法定刑とは、例えば、刑法第199条の殺人罪であれば「死刑
同じ「1人死亡の傷害致死」でも全く異なる刑
今回問題となった幼児虐待事件では、傷害致死罪が認定されたわけですが、最近話題になった同様の刑事事件で言えば、「鴻巣市乳児ゆさぶり暴行事件」(父親が生後1か月の乳児に揺さぶるなどの暴行を加え死なせた事件)では、傷害致死罪に問われた無職の父親が懲役7年(求刑懲役8年)を言い渡されました。また「六本木襲撃事件」(東京六本木のクラブで、暴走族のメンバーらが、グループと対立する人物と間違えて無関係の男性を金属バットなどで殴り死亡させた事件)では、メンバーの一部が傷害致死罪で、懲役13年(求刑懲役15年)を言い渡されました。さらに、「梅田ホームレス襲撃事件」(大阪・梅田で、少年らがホームレスの男性を襲い殺害した事件)では、少年らに懲役5年以上8年以下などの不定期刑を言い渡しています(少年の場合には、あらかじめ刑期を定めず改善状況に応じて刑を終了させる不定期刑が定められています)。このように、同じく1人の命が失われた傷害致死事件であっても、言い渡される刑が全く異なるわけです。
様々な事由で決まる刑の重さ
では、どのようにして、刑の種類とその量は決められるのでしょうか。
量刑は、まず、法定刑として、2種以上の刑罰が選択的に規定されている場合、例えば、刑法第235条の窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされており、「懲役」と「罰金」という刑罰が選択的に規定されていますが、この場合には、いずれかの刑の種類の選択を行うこととなります。例えば、被害が少額の万引きなどでは、懲役刑にはならず罰金だけで済むことが多いでしょうが(そもそもお店との間の私的な示談で済み、刑事事件に発展しないことも多いと思いますが……)、被害額が大きかったり計画的であったりすれば懲役刑が選択されます。
次に、刑を加重したり減軽したりする事由がある場合には、それに基づいた加重減軽を行うことになります。刑法の規定には、いくつかの加重減軽事由が規定されており、<1>再犯加重、<2>法律上の減軽、<3>併合罪の加重、<4>酌量減軽の順序で加重減軽されることとなります。
<1>の「再犯加重」とは、1度刑を科されたにもかかわらず再び犯罪を行ったような場合には、強い非難が加えられるべきという理由と、犯罪を繰り返す行為者の反社会的危険性に対して保安的観点から対処する必要があるとの理由から、その罪について法定された懲役の長期の2倍まで刑を加重することができるとされています。例えば、窃盗罪では、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされていますので、再犯の場合には、10年の2倍である20年の懲役まで刑を加重することができることになります。
<2>の「法律上の減軽」には、減軽が必要的な場合と裁量的な場合があります。必要的な場合とは、心神耗弱、中止未遂、従犯などがあり、裁量的な場合とは、過剰防衛、過剰避難、法律の不知、自首などがあります。皆さんがよく刑事ドラマなどで耳にするのは、過剰防衛(例えば、居酒屋で隣り合わせた客に因縁をつけられて、相手が殴りかかって来たので反撃したら、思わぬ大けがをさせてしまったなど)や自首などかと思いますが、刑事事件では、その他の事由も含めて問題とされます。
どのように減軽されるかは細かい話ですので割愛しますが、例えば、有期の懲役を減軽するときは、長期及び短期の2分の1を減ずるとされていますので、「1年以上10年以下の懲役」の法定刑である営利目的誘拐罪において、自首した場合には、「6月以上5年以下の懲役」に減軽されることとなります。
<3>の「併合罪の加重」とは、確定判決を経ていない2個以上の罪を犯している場合を指すのですが、これも難しい話になりますのでここでは割愛します。
<4>の「酌量減軽」とは、犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、上述の法律上の減軽と同様に、刑を減軽できるものです。犯罪の情状とは、犯行の動機、方法、結果、社会的影響や、犯人の年齢、性格、経歴、環境、犯罪後における犯人の態度などとされています。酌量減軽をするか否かは、専ら裁判所の裁量権に属するとされており、法律上加重されたり減軽されたりする場合でも、酌量減軽することができます。例えば、営利目的誘拐罪で自首した犯人が酌量減軽される場合、法律上減軽された「6月以上5年以下の懲役」が、さらに「3月以上2年6月以下の懲役」に減軽されることとなります。
このように法定刑に加重減軽を施して得られたものが処断刑といわれるものであり、この処断刑の範囲内で裁判所は宣告刑を決定して言い渡すこととなります。そして、刑法には量刑の基準に関する包括的な規定は置かれておらず、情状や求刑、量刑に関する関係者の嘆願書など、法廷に現れたすべての事情を
裁判所が大きな裁量を持っている
実際の量刑を行うのは個々の裁判所ですので、裁判所または裁判官の考え方によって、同じ犯罪で同じような情状であっても量刑に差が出てくることは十分に予想されます。しかし、同じ犯罪で同じような情状の場合において、量刑に著しいばらつきがあると、被告人に強い不公平感が生じることとなりますし、刑事司法に対する社会の信頼をも失うことにもなりかねないことから、実務では、「量刑相場」によって具体的な量刑が行われているといわれています。
量刑相場とは、経験的に形成された実証的な基準などといわれており、法定刑に相当な幅のある法制下で公平な量刑判断をしようと思えば、必然的に、このような基準が生まれてくるものとされています。
量刑相場は、同種事案を集めて量刑の傾向を探る作業の中から導かれます。裁判所または裁判官は、個別の事情のみではなく、過去の裁判例の量刑に関する資料を参考にして量刑を行いますが、過去の裁判例をもとにした個別の量刑がまた裁判例となり、これらが、時代を追って次々と積み重ねられて量刑相場が形成されていくこととなります。
また、量刑の実務においては、検察官の「求刑」も重要な役割を果たしているといわれています。求刑とは、検察官の事実及び法律の適用に関する意見の一部として、検察官が具体的な刑罰の種類及び刑量に関する意見を述べることを言います。この求刑と具体的な量刑判断との間には一定の相関関係があると言われており、一般的には、具体的な量刑判断は求刑から2~3割減軽されたものになることが多いと思われます。検察官の求刑も量刑相場を意識してなされていることから、量刑判断と相関関係があることには合理的な理由があると考えられています。また、求刑には、被告人にとって量刑の上限を予測させることとなり、具体的量刑が求刑との対比でどの程度であったかによって、被告人及び弁護人が量刑上考慮するよう求めた事情をどの程度考慮してもらえたのかを推測させるといった役割も担っていると考えられています。
求刑超え判決
しかし、量刑の判断は、裁判所または裁判官の専権事項であり、求刑に拘束されるわけではありません。そして、2009年の裁判員裁判制度導入以降、求刑よりも重い量刑の判決、すなわち、冒頭の新聞記事に出てきた、いわゆる「求刑超え」の判決が、実際に増加しています。最高裁判所が、今年3月末までに出された判決について、殺人、殺人未遂、傷害致死、(準)強姦致傷、(準)強制わいせつ致傷、強盗致傷、現住建造物等放火、覚せい剤取締法違反の8罪名に絞って「求刑超え」の割合を調査したところ、裁判官による裁判では2008年4月以降で「求刑超え」とされた被告人は2人のみで全体の0.1%にとどまっているのに対し、裁判員裁判では43人で全体の1%に達していたとの結果が出たとされています。
今回、これら裁判員裁判で顕著に表れるようになった求刑超え判決について、最高裁判所が一定の基準を明確にしたものが、冒頭で話題にした判決であるわけです。
第1審判決からうかがえる今回の事件の悪質性
相談者が言及している傷害致死事件では、幼児を虐待したとして傷害致死罪に問われた両親に対して、第1審の裁判員裁判で懲役10年の求刑に対し、求刑の1.5倍にあたる懲役15年の判決が言い渡され(大阪地方裁判所・平成24年3月21日判決)、第2審もこれを支持しました(大阪高等裁判所・平成25年4月11日判決)。
第1審判決の認定した犯罪事実の要旨は以下のとおりです。
「被告人両名は、かねて両名の間に生まれた三女にそれぞれ継続的に暴行を加え、かつ、これを相互に認識しつつも制止することなく容認することなどにより共謀を遂げた上、平成22年(2010年)1月27日午前0時頃、大阪府内の当時の被告人両名の自宅において、被告人A(父親)が、三女(当時1歳8か月)に対し、その顔面を含む頭部分を平手で1回強打して頭部分を床に打ち付けさせるなどの暴行を加え、その結果、急性硬膜下血腫などの傷害を負わせ、同年3月7日午後8時59分頃、同府内の病院において、三女を急性硬膜下血腫に基づく脳腫
そして、第1審判決は、量刑の事情について次のように指摘しています。
まず、犯した罪に見合った刑を定めるという観点から特に重視した事情として、<1>親による児童虐待、特に幼児虐待の傷害致死の行為責任が重大であること、<2>態様が甚だ危険で悪質であること、<3>結果の重大性、<4>身勝手な動機・不保護を伴う常習的幼児虐待、<5>被告人両名の間で刑事責任に差異がないことが挙げられ、またそれらに加えて、被告人両名に不利益なものとして相応に考慮した事情として、<1>堕落的な生活態度、<2>罪に対する被告人両名の態度、<3>責任の一端を次女になすりつけるような供述をしていることなどが挙げられています。
判決文においては、上記各事情につき詳細な判示が
「被害女児は、平成21年(09年)春ころから約9か月間もの長期にわたり、自分を守ってくれるはずの両親である被告人両名から、抵抗したり逃亡して助けを求めたりすることのできない状態にあるにもかかわらず、理不尽な暴行を繰り返されてそれが常態化し、その暴行が激化した末に、悲惨悲痛な死を余儀なくされたものである。その間の肉体的苦痛はもとより、逃げ場のない孤独や絶望を抱いた被害女児の精神的苦痛は筆舌に尽くし難いものであったとうかがえ、最後には無限の可能性を奪われるに至ったのである。被害女児の無念さは察するに余りあり、結果は極めて重大である」
両親とも求刑を超える量刑となった点について
裁判所は次のように判示しています。
「裁判員と裁判官は、証拠から認められる事実に照らして、量刑の考慮要素を一つ一つ冷静かつ慎重に検討することに努めた。そして、前記1及び2の各事情に照らすと、親による常習的幼児虐待の中で被害女児を死に至らしめた行為責任は
この点、最高裁判所「裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会」第13回資料によれば、傷害致死罪の裁判官裁判における量刑のピークは「懲役3年超5年以下」であったのに対し(2008年4月~11年8月)、裁判員裁判における量刑ピークは「懲役5年超7年以下」であり、しかも「7年超9年以下」もほぼ同水準の比率となっています(09年8月~11年8月)。また、今年6月時点で裁判所のデータベースに登録された子供の虐待死事件は約70件で、大半は懲役9年以下であるとの報道もなされています。こういった過去の傾向からみても、第1審及び第2審の懲役15年というのは、量刑相場からは乖離していることは間違いありません。
続く大阪高等裁判所の判決
上記判決を受けて、量刑不当などを理由に、両親から控訴がなされましたが、第2審の大阪高等裁判所も原判決を支持し。量刑の点については、「当裁判所も、以上のような原判決の評価及び判断が誤っているとまではいえず、その結論としての上記量刑判断もやむを得ないものであって、破棄しなければならないほどに重すぎて不当であるとまではいえないと考える」と判示しています。
これら判決では、保護すべき立場にある親が、幼児を理不尽な暴行などで虐待することによって死亡させた傷害致死事件で行為責任は重大であるとした上で、育児放棄に等しい不保護を原因とする、発育不良・低体重状態にあった1歳8か月の無抵抗の女児を強い勢いで殴りつけた行為の態様が、殺人罪と傷害致死罪の境界線に近いものと評価するのが相当であると判断し、通常の傷害致死事件とは異なって、悪質性がまったく違うため、児童虐待事犯に対しては、厳罰で対処することが社会情勢に適合すると考えているわけです。ある意味で、裁判員裁判制度において期待されている「市民感覚」が反映された判決と考えられます。ちなみに、前述「裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会」第13回資料によれば、殺人罪の裁判官裁判及び裁判員裁判における量刑のピークは「懲役11年超13年以下」となっており、第1審、第2審の判断は、殺人罪の量刑に近い判断をしているわけです。
最高裁判所は、裁判員裁判でも公平性が必要と判示
これに対して、最高裁判所は、第1審判決の評価について、これらが誤っているとまではいえないとした第2審の判断は正当であるとしながら、被告人両名を各懲役15年とした第1審、第2審判決の量刑は是認できないとして、第1審、第2審判決を破棄し、父親を懲役10年、母親は実行行為に及んでいないことを理由に懲役8年と
最高裁判所は、以下のように、裁判員裁判によって量刑に変化がでることは認めていますが、「裁判員裁判といえども、他の裁判の結果との公平性が保持された適正なものでなければならない」と明確に判断しています。
「我が国の刑法は、一つの構成要件の中に種々の犯罪類型が含まれることを前提に幅広い法定刑を定めている。その上で、裁判においては、行為責任の原則を基礎としつつ、当該犯罪行為にふさわしいと考えられる刑が言い渡されることとなるが、裁判例が集積されることによって、犯罪類型ごとに一定の量刑傾向が示されることとなる。そうした先例の集積それ自体は直ちに法規範性を帯びるものではないが、量刑を決定するに当たって、その目安とされるという意義をもっている。量刑が裁判の判断として是認されるためには、量刑要素が客観的に適切に評価され、結果が公平性を損なわないものであることが求められるが、これまでの量刑傾向を視野に入れて判断がされることは、当該量刑判断のプロセスが適切なものであったことを担保する重要な要素になると考えられるからである。この点は、裁判員裁判においても等しく妥当するところである。裁判員制度は、刑事裁判に国民の視点を入れるために導入された。したがって、量刑に関しても、裁判員裁判導入前の先例の集積結果に相応の変容を与えることがあり得ることは当然に想定されていたということができる。その意味では、裁判員裁判において、それが導入される前の量刑傾向を厳密に調査・分析することは求められていないし、ましてや、これに従うことまで求められているわけではない。しかし、裁判員裁判といえども、他の裁判の結果との公平性が保持された適正なものでなければならないことはいうまでもなく、評議に当たっては、これまでのおおまかな量刑の傾向を裁判体の共通認識とした上で、これを出発点として当該事案にふさわしい評議を深めていくことが求められているというべきである」
第1審について「甚だしく不当な量刑判断」と判示
その上でさらに、最高裁判所は次のように判示し、第1審及び第2審の量刑判断を批判しています。
「こうした観点に立って、本件第1審判決をみると,『同種事犯のほか死亡結果について故意が認められる事案等の量刑傾向を参照しつつ、この種事犯におけるあるべき量刑等について議論するなどして評議を尽くした』と判示されており、この表現だけを
これを本件についてみると、指摘された社会情勢等の事情を本件の量刑に強く反映させ、これまでの量刑の傾向から踏み出し、公益の代表者である検察官の懲役10年という求刑を大幅に超える懲役15年という量刑をすることについて、具体的、説得的な根拠が示されているとはいい難い。その結果、本件第1審は、甚だしく不当な量刑判断に至ったものというほかない。同時に、法定刑の中において選択の余地のある範囲内に収まっているというのみで合理的な理由なく第1審判決の量刑を是認した原判決は、甚だしく不当であって、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる」
つまり、第1審及び第2審は、「児童の生命尊重の要求を含む社会情勢にかんがみ、本件のような行為責任が重大と考えられる児童虐待事犯に対しては、今まで以上に厳しい罰を科することが法改正や社会情勢に適合する」として、従来の量刑相場を超える懲役15年を選択したのに対し、最高裁判所は、従来の量刑相場を前提とすべきではないのであれば、具体的・説得的な理由を示す必要があるのに示されていないとして、第1審及び第2審判決を破棄したわけです。
裁判員裁判の意義
裁判員裁判は、市民の日常感覚や常識を裁判に反映させるとの趣旨で導入された制度です。最高裁判所判決も、「裁判員制度は、刑事裁判に国民の視点を入れるために導入された。したがって、量刑に関しても、裁判員裁判導入前の先例の集積結果に相応の変容を与えることがあり得ることは当然に想定されていたということができる。その意味では、裁判員裁判において、それが導入される前の量刑傾向を厳密に調査・分析することは求められていないし、ましてや、これに従うことまで求められているわけではない」と明確に判示しており、必ずしも市民感覚を反映させること自体を否定しているわけではありません。今回の判決も、従来の量刑相場を前提とすべきではないのであれば、具体的・説得的な理由を示す必要があるという原則論を述べただけとも言えます。
裁判長を務めた白木勇裁判官は、補足意見で、「量刑判断の客観的な合理性を確保するため、裁判官としては、評議において、当該事案の法定刑をベースにした上、参考となるおおまかな量刑の傾向を紹介し、裁判体全員の共通の認識とした上で評議を進めるべきであり、併せて、裁判員に対し、同種事案においてどのような要素を考慮して量刑判断が行われてきたか、あるいは、そうした量刑の傾向がなぜ、どのような意味で出発点となるべきなのかといった事情を適切に説明する必要がある。このようにして、量刑の傾向の意義や内容を十分理解してもらって初めて裁判員と裁判官との実質的な意見交換を実現することが可能になると考えられる。そうした過程を経て、裁判体が量刑の傾向と異なった判断をし、そうした裁判例が蓄積されて量刑の傾向が変わっていくのであれば、それこそ国民の感覚を反映した量刑判断であり、裁判員裁判の健全な運用というべきであろう」と述べています。
つまり、適切な評議が行われるよう、裁判官に対して、量刑相場の持つ意義を裁判員に十分に理解してもらった上で評議が実施されることに努めるべきであるとの姿勢を示したのであって、決して、裁判員の市民感覚を否定したものではないとも考えられるわけです。
今後は、量刑において、裁判員制度の市民感覚を反映させるという側面と、刑事裁判の公平性の観点から先例を参考にする側面のバランスを、どのようにとっていくのかが課題となってくるのではないかと考えられます。